�@�@
��������ᇁ@ 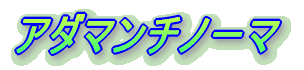 �@���a�̋L
�@���a�̋L
�`�@����͕��s���̋ؓ��ɂ���n�܂����@�` �@�@ �@�@ �@�@ |
| �@�Q�O�O�Q�i�����P�S�j�N�@�H�P�O����������A�E�r�����i�X�l�j�ƒ����i�t�N���n�M�j�ɋؓ�����������悤�ɂȂ����B���Ƃ��Ƌؓ��̎��ł��������ߋؓ��ɂ�x�X�N�����A�����C�ɂ͂��Ȃ������B�H�̐A�ւ��V�[�Y���œ����߂������ȂƎv�����x�ł������B �����������āA�{��i���A�a����t�s�S�ƂȂ�A���̂P�O�N�͏T�ɂR���l�H���͂ɒʉ@���Ȃ���삵�Ă����j�������œ]�|���A���̑Ŗo�ɂ������ŐQ�������ԂƂȂ����B �@�P�Q���n�ߓˑR�Ɏ������h�J�Ⴊ�~��ς���A���S�͂���R�쑐���A�A�ؔ��Ȃǂ̈ꕔ���~�����菀���O�������̂Őቺ�ŒւȂǂ��}�܂ꂵ���B��~�������Ȃ���̐A�ؔ��̈ړ��ɂ͎�Ԏ��A��N�ɔ�ב啪�x��Ă��܂����B �@ �@�Q�O�O�R�i�����P�T�j�N�@�������}���Ă��r�̒ɂ݂͎��܂炸�P�Ȃ�ؓ��ɂł͖����Ǝv���A�P���U���ɋ߂������`�O�Ȉ�@����f�����B �V��t�̓����g�Q���ʐ^�����āA�u�@��ᇂō��̈ꕔ���n���Ă����̂ŁA�����͐l�H���ŕ⋭����K�v�����邾�낤�B�ǐ��Ȃ̂Œɂ݂͏t�����Ēg�����Ȃ�Ύ����@�v�ƌ����A�O�̂��ߌ����̃J���V���E���Z�x�����邽�߂ɂƌ��t�����������B�̌����ĂS����̌��ʂ͐���l�ŁA�u�@������������������v�@�v�ƌ����āA�ؓ��ɗp�̓h�����n���ꂽ�B ���̎��͎�芸�����z�b�Ƃ��A�������ӂ̌��Ƃ̎U���ɂ̓o���e������h�邩���z���\���āA���̏���T�|�[�^�[�ŕ����A�G�ɂ͋��͂ȃh�C�c���̃T�|�[�^�[�����ďo�������B �����āA���̓~�̓X�L�[�͏o���Ȃ��̂ŁA�v�������z�[���y�[�W�̍쐬�ɒ������邱�Ƃɂ����B �@�R���ɂȂ��Ă��r�̒ɂ݂͑�������ł��������A�v���C�h�����I���c�����ۂ����{��̉���͓�l�W��łȂ��Əo���Ȃ���ԂƂȂ����B�₪�ĐH�������Ȃ��Ȃ�A�s���Ǐo�Đ�������S���U�����A�Â��Ɏ���̃x�b�h�ő�������������B �s�N�X�Q�A�V���Ɛf�f���ꂽ�B���킽���������V�̂Ȃ��A�Ȃ̘J��Ɋ��ӂ��Ō�܂Őe�̖ʓ|���łꂽ���ƂɈ��g�����B �@��̒r��|�����Đ���A�z�~�p�|���r�����Ƌ������ڂ��B�~�G�͉Ƃ̒��Ɏ�荞��ł����A�ؔ����O�ɏo���A��͂��̒��̔��A����A�����╻�̘e�Őቺ�ɑς�����R�̔��A�������ꂼ��̒�ʒu�ɉ^�яo���B�t�͐A���ւ��̍œK���Ȃ̂��������܂Ŏ肪���Ȃ��B���̎U���ƍ��킹�āA�g�ɒ����Ă��������v�͂P���T����O���ƂȂ����B �@�Ж�͑����āA�T���P�S���ɂ��������S���Ȃ����B�X�O�A�����K���ł������B��ɂ͋r�̂��Ƃ�m��ꂸ�ɂ����A���V�̐Ȃł�������������A�w�̊K�i�͎萠��ɂ��܂��Ă���Ƃ̎v���ŏ���~�肷���Ԃł������B 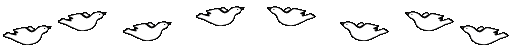
�@�Ă̒�A�u�E�r�͍��ܐ��O�Ȃ̂Ő�Δ�Տd�v�ƌ����A�����@�Ԉ֎q�����ƂȂ����B ������p�Ő؎������ᇑg�D�͐V����w�ɑ����A�ǐ��������������҂����B  �E�r�͌Œ肵�ĕ�т������i���̎ʐ^�j�A���C�ɂ͂͂��ꂸ�A�|���܂�킹�G��Őڒ��e�[�v�Ŏ~�߂ăV�����[�𗁂т�B�ړ��͎Ԉ֎q�ŁA���ʂ�g�C���ł͈ꎞ�I�ɍ��r�ł̕Б������̂݁B �E�r�͌Œ肵�ĕ�т������i���̎ʐ^�j�A���C�ɂ͂͂��ꂸ�A�|���܂�킹�G��Őڒ��e�[�v�Ŏ~�߂ăV�����[�𗁂т�B�ړ��͎Ԉ֎q�ŁA���ʂ�g�C���ł͈ꎞ�I�ɍ��r�ł̕Б������̂݁B�i���̏�Ԃ͈Ȍ㗂�N�Q���Q�P���܂ő������ƂɂȂ����B�j ���@�E��p�E�_�H�ECT�EMRI�A���ׂĂ����̌��ł��������A��t���Ō�t���Ⴍ�ĔM�S�ŗD�����������A�U�K�̂U�l�����͐��`�O�ȕa���Ȃ̂Ŋ��҂̊F����Ƃ��������ǂ��Ȃ�ĉ��K�ł������B �@�P�R����ɁA�厡��̙B�c�搶�i�R�R�H�j����f�f���ʂ��`����ꂽ�B ������ᇂŁA�����ɐV����w�t���a�@�̐��`�O�ȊO������f����悤�Ɍ����A�ň��̗\���������蜱�R�Ƃ����B�@(�E_�E;)�E�E�E �@�U���P�Q�����A�`��i�Ȃ̒�j�ɗ���ŐV���܂ő����Ă��炤�B�i�䂪�Ƃɂ͎����Ԃ������A���q�͋��s�ɁA���̌Z����߂��ɋ��Ȃ��̂ŁA�Ȍ㉽����`��̐��b�ɂȂ�L������B�j ��w�a�@�ō���ᇐ��̐��z�搶����f�@���A�u�A�_�}���`�m�[�}�Ƃ�����������������v�̋^�����ɂ߂ċ����Ɛf�f���ꂽ�B���@�̎�z�����肢���ĕK�v�ȏ����������B
�@�a���͐V�z���ꂽ�P�Q�K���Ă̐��ٕa���S�K�i���ȂƐ��`�O�ȍ����j�̂S�P�U�����i�S�l�����j�B �ݔ����ǂ��Y��Ńz�e���̂悤�Ȉ�ۂł������B �ߌ�ɂ͒S�����Ē�����t�S���̐搶�����������ŗ������ꂽ�B �@�@���Ǒ��e�܂��g���ĕ��ː��B�e�iCT�j������A �@�AMRI�@�������ēx���A����ɋ߂��Ƃ���Ɏ�ᇂ̍����Ȃ������ׂ�A �@�B�������@�̊o�傪�K�v���B �܂��A��a�������Ƃ������A�R���A�R�u�Ȃǂ��������Ƃ��m�F���ꂽ�B �R���̐搶���͐쓇�A�n�ӁA�h�X�̎Ⴂ��t�B�ŁA���̌㉽���ƋC�����Ă��炢�A �Z���𗬂̒��ł��傢�ɗE�C�Â����A�Ԃ߂��A�a�ɕ����ʋ����C������^�����邱�ƂƂȂ����B �@ �@�U���P�W���A�������Q�S���Ԃ̐��m�~�A�i�R���ܓ��^�ɔ����t���@�\�ׂ�ׁj�B �@�U���P�X���A���ɍ̌��B�[���ɂ͐��z�搶���A�u�@��ᇕ��������ɂ��L���Ă��̕����������Ɛ���ƁA�����c���Ă����Ȃ��炸�������o���Ȃ��Ȃ����ƁB�@�G���Őؒf���A�`���𒅂���ق����@�\�I�ɂ͗ǂ�������Ȃ����ƁB �ǂ��炪�ǂ����͖{�l�̐S�̖�����B�v�Ƙb���ꂽ�B ��A�Ȃɓd�b����ƁA�]�ڂ�Ĕ��̐S�z�������Ȃ�A�v�������ؒf�̕����ǂ������ƁE�E�B �X���������������K���̓C���z�[���g�킸�Ƀe���r�����A�������ɐQ���Ȃ������B �@���@���������A�S���ň����͌ʂɗ���������f�A�������̗\�����������ꂽ�B ��i��Â�S����w�a�@������A��w�҂Ƃ��Ă̌����ƁA��p��O���f�Â����钆�ŁA�y�����x�ݖ��������̓��@���҂�f�܂��B��ςȌ����ł��邱�Ƃ�m�����B �܂��A�Ō�t�̊F������V���̃`�[������Ɏ��B�̕a����S�����A�R��㐧�ł���܂���ϖZ�����B���@�����������̂ŔY�݂������^���ɕ����Ă��ꂽ��A�ׂ₩�Ȕz�����A�������邢�Ί�ŋC������O�����ɂ����Ă�������B �ޏ���̗D�ꂽ���Ƃ̏o����M�d�ȑ̌��ƂȂ����B  �@�U���Q�Q���A���j���Ȃ̂ɐ��z�搶�`�[������������A �a���̑��k����MRI�̎ʐ^�i����a�@���玝�Q�����R�s�[�j�������g�Q���ʐ^�i�E�̉摜�j���f���āA�������ꂽ�B �@�@������ᇁE�A�_�}���`�m�[�}�̎�ᇕ��������ɂ��L�����Ă���^��������AMRI���B��Ȃ����͂����肷��B �Ĕ��h�~�̂��ߑ���̍��܂Ő؏�����悤�ɂȂ�������o�����A���w�͓��������S�ɂ͎��R�ɂȂ�Ȃ��B �@�A�����c����p�i���������̍���؏����A�����ׂ̍��C��������Ĉڂ��j�͂W���Ԉʂ��A�����ǂ��N�����댯��������A�p����������S�ɐڍ�����܂Ŏ��Ԃ�������B �@�B�G���Őؒf����ق����ȒP�����ɂ݂��c��ꍇ���L��B �`���͋@�\���ǂ��Ȃ��Ă��Ă���B �A�ƇB�̑I���͐S�i�l���ρj�̖�肾����Ɩ{�l�̌��f�𑣂��ꂽ�B �@ ���́A�u�\�Ȍ��葫���c����p����]����B���ׂ̈ɑ���̎��R�����������悤�ɂȂ��Ă��d���Ȃ��B�@�\�̗ǂ����������A�L�邩�������̕�����{�I�ɏd�v������B�����c����p�������ȏꍇ�ɂ͕G���ł̐ؒf���[������B�v�Ǝv�����q�ׁA�搶�����������ꂽ�B �@�U���Q�S���A���`�O�Ȓ��̉�����������f�ɗ���ꂽ�B�i���T�Ηj�Ƌ��j��������f�̓��ŁA�s�݂̂Ƃ��͏������̐搶�������Ă����������B�j�@�ߑO���ɁA��p�ɔ����������ȊO������f�A������n�����f�Ŋm�F����B �������`���O�ȊO������f�i�畆�ڐA���l���āj����p���e���m�F�B �ߌ�A���e�܂��g����MRI�i���C���e���@�B�d���g���g���ďc�E���E�߂Ǝ��R�Ȋp�x����ڂ����l�̂̒f�w����`���摜�f�f�@�ŁA���������j�����B �[���ɐ��z�搶���������A���Ǒ��e�����i�ו��ɂ킽�錌�ǂ̑��s�����邽�߂ɍs���j�̐���������A���ӏ��ɃT�C������B �@�U���Q�T���ACT�����i�R���s���[�^�f�w�B�e�@�AX���Ől�̂̉��f�ʗ葜��`���j����B�@�����ɔ����āA�\�a���i�r�̂����j�̒�т�����B �@�U���Q�U���A�O��悭���ꂸ�B���H�����Ōߌ�P���A���Ǒ��e�����̂��߂�T���т𒅂��a�߂ɒ��ւ��A�_�H�`���[�u�ƔA�̊ǂ�ʂ��ăx�b�h�ɐQ���܂܌������ֈړ������B�B�e�͂P���ԁA�����ȂNJ܂߂Ė�Q���Ԃ̋ꂵ�������ł������B ���r�̂����ɋǏ��������ē����ɃJ�e�[�e����}�������e�܂𒍓�����B�r���M���Ȃ�A�ؓ����d�����Ĉӎu�ɔ����ĐU�����N�������B�B�e�̂��ߓ������Ȃƌ����A����H�������ăK�}������@(>_<)�B ���łɎ��̉E�r�͎�ᇕ����c��オ��A�G��ꂽ��B�e�̂��ߋr�̌�����ς����肷��̂��ς��������ɂ��Ȃ��Ă����B�Ō�Ɍ����䂩��x�b�h�Ɉڂ����Ƃ����ɂ��č����܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����v�����B�@���̒����J���J���Ɋ������B �@�a���̃x�b�h�ŗ[�H���܂ň��Âɂ���B�H�~�͂��邪�A�܂��������Ƃ��o���Ȃ��̂ōȂɃX�v�[���Ō��ɉ^��ł��炤�B��P�O���ɂ͎��͂ő̂̌�����ς��Ă悢�Ƃ���ꂽ���A�E���ɂ͉��Ƃ��Q�Ԃ�ł������A�E�r���ɂ��č����ɂ͐Q�Ԃ�ł��Ȃ��B�E�r�͉��̂悤�ɏd�������A�����グ�邱�Ƃ��o���Ȃ��B ��Ӓ������ɐQ���܂܂قƂ�ǖ���Ȃ������B �@���Q�V���A�E�r�ɗ⎼�z��\���ĖႤ���x�b�h�ւ̏オ��~�肪��ςɂȂ����B�ߌ�ɕa���̊Ō�t�Ǝ�p���̊Ō�t����R�O���̎�p�ɂ��Đ���������A�����Ȉ�t����f�ɗ������u�������ӏ��v�ɃT�C������B �@�U���Q�W���A�Ȃ����Ȃ����A���z�搶����p�̐����i�C���t�H�[���h�R���Z���g�j���A�u�E����������ᇁi�A�_�}���`�m�[�}�j�̐؏��A���E�畆�̈ڐA�A�n�O�Œ�p���s���v��p���ӏ��ɃT�C������B�@�����̎�ȓ��e�͈ȉ��̒ʂ�B �@�@�Ĕ���h��������ᇕ����ӂ̌��S�ȍ��������܂߂Đ؏�����B �@�A�E�r�C�������Ǖt���ňړ������A���r�C��������ĈڐA���A �@�@����ڍ������ɒ����i���̍��j�̈ꕔ���ڐA����B �@�@���ߌŒ�Ƃ��n�O�Œ�ŕ⋭�B�@ �@�B�ؗ͂̒ቺ�E����̒ቺ�E�m�o��Q�����N���肤�邱�ƁB�@ �@�C�������A�_�o�E���Ǔ��̑����A�x���E�x�[�Ǔ������������N���肤�邱�ƁB�@ �@�D�K�v�Ȃ���畆�ڐA��A�������A�ؒf�̕K�v�ȏꍇ�����邱�ƁB�@ �@�E���ː���R�����ɂ�鎡�Âp����ꍇ�����邱�ƁB�@ �@�F��w�a�@�̐��i����A��w���̌��w��A �@�@�؏�������ᇕ��������p�ɕۑ��E���p���邱�Ɠ��ɂ��Ă̓��ӂ����߂�B �Ȃǂ̓��e�ō��܂ł��b����Ă������Ƃ̍ŏI�I�Ȋm�F�ł��������B �@ ����a�@�֓��@���Ă��炷�łɂP�����A���̊Ԃɂ���ᇂ͑��B���A�ɂ݂������Ȃ��Ă����̂ŁA��p�ւ̕s���͖����A�ނ��둁����p���ăA�_�}���`�m�[�}����菜���Ăق����Ƃ������҂̕����傫���Ȃ��Ă����B �@��p�O���͓��j�����������A�x�c�N�v�������i����ᇐ��`�[���̒��S�ƂȂ�搶�j����f�ɗ����āu�@���S���Ė����̎�p��҂悤�@�v�b���ꂽ�B �̏d�T�V�C�Okg�A�̉��R�U�C�S�x�A�����P�P�T�|�U�W�A�@�V�����[�𗁂тĐÂ��ɉ߂����B �@�U���R�O���i���j���j�A��p�����A�����͂��Ȃ��ėǂ��Ƃ̂��ƁB �U���N���A�g�C���A���ʁA�E���  ���ς܂��āAT���тƕa�߂ɒ��ւ���B�V���R�O����b�����̒��˂�łƋْ������A�����Ȃ����B ���ς܂��āAT���тƕa�߂ɒ��ւ���B�V���R�O����b�����̒��˂�łƋْ������A�����Ȃ����B�@���W���A�S�l�����̂S�P�U��������A�x�b�h�ɐQ���܂�p���ֈړ�����B ��p���Ԃ͂W���Ԃƕ����Ă������A�����E�㏈���E��������̉E��p���ʌ�̃����g�Q���B�e�i���̉摜�j�Ȃǂ������āA�a���i�i�[�X�X�e�[�V�����e�����j�ɋA���Ă����̂���̂W�����ł������B�@ ���͂����P�Q���Ԕ��̋L���������A��������ɂ݂���ɂ��܂����������鎖�����������B �@��p���ł́A�S�d�}�⌌���v�Ȃǂ̋@������t���A�����Ȉ�t���S�g�����i�_�H�ŐÖ������������j���d���O�����i�ׂ��ǂ����̐Ґ��̋߂��ɓ���āj�p���čs���A�l�H�ċz�p�̃`���[�u��������A�ɓ����B ���O�̐����ʂ�̎�p�������ɍs���A���������ƕ������ꂽ�B �E�r�R�Vcm�ƂVcm�A���r�Q�Ucm�A�����Ucm��؊J���A�����P�{�؏��A�C���Q�{�������̈ꕔ���ڐA�i�ڍ����ɂ̓`�^���̃N�M���Q�{���v�S�{�ł��A�i�v���ߍ��݂Ƃ���j�B�A���͏������Ă��������ۂɂ͍s�킸�A�畆�ڐA���\�肵�Ă��������{����K�v�����������Ƃ̂��Ƃł������B�@�܂��ɐ_�ƁI�@ ��p�̏́A�؏�������ᇂ̎ʐ^�Ȃǂ��ȂɌ����Đ��z�搶���������ꂽ�B �i�d���O�����̊ǂ́A���̌�Q���Ԏg�p���Ē��ɖ�𒍓����A�p��̒ɂ݂��܂����������邱�ƂȂ��A�L��A���S�����B�j �@�g�͓̂������Ȃ����A���̕�������B��тɂ܂ꂽ�r���n�O�Œ�̋������t�����Ă��邪�A���̎w�������Č��F���悭�A�͂����������̈ӎu�œ��������B�����悤�̖��������������ݏグ�ė����B �@ �@���̖�͗����܂ŐS�d�}�A�_�H�R��A�@����A�֊ǂ�����_�f�z���}�X�N������B�܂��A����\�h�̂��߁A�����ւ̎h���ɂ��[���Ö��̌������悭����@����g�p�i�����ԁA�G�R�m�~�[�N���X�nj�Q�\�h�j�����B�������Q�W�x�ɐݒ肳��Ă���A��Ӓ��M���Ċ����o�Ď~�܂炸�f�����ۂ������B �S���̊Ō�t��M����͂S���ɍ̗p�ɂȂ�������̐V�l�Ȃ̂ő�ς������Ǝv���B �������������Ȃ������̂ŁA�Ȃ͋A��ł����a���Ɉꔑ����������Ȃ������悤���B �@ �@�V���P���A�����̃o�X�� �����A���̎U���A�C���R�ƌ�E�����E�M�ы��̐��b�A���S��������R�쑐�E�Ԗ̐��������������ŁA ���@���͂P�������ɂ͐V���ɗ��Ă��ꂽ�B�@���ӁI���ӁI �@�������ɁA���z�搶���������A�u�@��F���悭���C�����@�v�ƌ����A�@���悳�����B�ˑR�u�@�����グ�Ă݂Ȃ����@�v�ƌ����Ď��G���ꂽ��A�s�v�c�ɑ�����ɂ����邱�Ƃ��o���A�����ł��r�b�N�������B ���̐搶�͐_�̎�Ɩ��@�̌��t���g���̂��낤���ƁH�@ �̉��R�V�D�T�x�����M�͂��邪�A������x�b�h�ŐH�����o����悤�ɂȂ����B �@ �@�V���Q�����A���̊��҂���̂��ߌ����o�Č��̂S�P�U�����ֈړ��B �r�֎��ɑ̂��x����̂Ɏg�����߃x�b�h�ɓS�_��̂��̂����t����ꂽ���A�����ȕ֊�Ńx�b�h��ł͏o�悤���Ȃ��B �@�V���R���A���w�Ö@�m��T���x�b�h�T�C�h�֗��Ă���A���w�ƕG�������n�r�����J�n�����B �n�ӈ�t���A���r�̕�т��͂����A�D���������ł��Ď��J�n�p���͂�A�������̂��߂̊ǂ���苎��B�@�@���̖D���������ł��Ċǔ����������B �R�����̓_�H���I���A�A�̊ǂ��͂����A�r�A�̓x�b�h����A�r���g�����ƂɂȂ����B �@ �@�V���S���A��X�搶�i�G�����̐搶�j����f����u�Q�Ă��鎞�ɉE�����p�ɂȂ�悤�ɁA���ĕ��������ق����ǂ��v�ƃA�h�o�C�X���ꂽ�B�����ɊŌ�t��Ha���v���X�`�b�N�̔���p�ӂ��Ă��ꂽ�B ��p��S���ԕ֔����������̂ŁA���܂��������Ă��炢�閰��O�Ɉ��B �@ �@�V���T���A������A���o�Ȃ��Ȃ蕠���p���p���ɒ����Ă����B�ߌ�P�����AHo����i�Ō�t�j�ɍ���̉��܂����Ă�����āA�Q���A�x�b�h��ŕ֊�ɂR��ɕ����āA�A���A�r�Ɉ�t�o���B�Ȃɏ������Ă��炢�A�y�ɂȂ����B�@ �ݔ����ǂ��Ȃ��ËZ�p�͓��i�����Ȃ̂ɁA�x�b�h�ł̔r�֕��@�͌��n�I�Ŏ���x�ꂳ���������͎̂��������낤���H �@�V���V���A��p�㏉�߂��Ԉ֎q�ɏ�鋖�����o��B�Ō�t�t���ň�K�̃��n�r�����֍s���B�@�ȕt���ŎԈ֎q�p�g�C���ֈړ��A���H���H���Œ������B�f���ɂ��ꂵ���I�@ �[���A���z�搶����u�������ʂ��ڂ������͂��čR���ܕs�g�p�ƂȂ�A�n�O�Œ��t���đމ@���A�����̗���a�@�ɒʉ@���Ă��ǂ����낤�B�v�ƌ���ꂽ�B ��A���E�P�Q�Ԃ肵���B �@ �@�V���W���A�Ō�tK����A���������Ă��炤�B�a���̐��ʑ�ŎԈ֎q�ɍ������܂܁A�������ɏ�肢�B�X���Ԃ�œ����X�b�L�����y���Ȃ����B�@�P�l�ŎԈ֎q�ɏ�邱�Ƃ������ꂽ�B �@ �@�V���X���A�̉��R�U�C�S�x�ƕ��M�ɖ߂�A�̏d�𑪂�����T�Tkg�i�n�O�Œ�P�C�Tkg�H���܂ށj  �ł������i��p�O�͂T�Vkg�j�B�@�E�r�̃����g�Q���B�e������B�@T���т���߂ăg�����N�X�ɂ͂��ւ���B �ł������i��p�O�͂T�Vkg�j�B�@�E�r�̃����g�Q���B�e������B�@T���т���߂ăg�����N�X�ɂ͂��ւ���BT�V���c���������Y�{���i�n�O�Œ肪�ז��ɂȂ�̂ʼnE�e�Ƀt�@�X�i�[��t���āA���͕R�Ō��ԁj���͂��āi�E�ʐ^�j�����X�����烊�n�r��������B �@�V���P�O���A�E�r�̈ꕔ�i�܂����Ă��镔���j���c�������������B �@�V���P�P���A���n�r�������t�����g���n�߂�B �@�V���P�Q���A�@���̗����X�œ������J�b�g���Ă��炤�B �e�ʂ��������ɗ����̂ŁA�Ԉ֎q�łP�Q�K�̃��X�g�����ɍs���B �@�V���P�S���A�Q�T�ԂԂ���V�����[�𗁂т�i�E�r�̓|���܂ŕ����āj�B �Ȍ㌎�j�Ɩؗj�̏T�Q�V�����[�̓��ŁA���̓����M�������^�I�����{�Őg�̐@��������B�@�g�̐@�������ł��C�����ǂ��A�T�b�p���Ƃ���B �@�V���P�V���A�x�c�搶�@�u�E�r��d�Ń��n�r�����A�Ԉ֎q�E���t��̎g�p�őމ@�ł���悤�ɂȂ邾�낤�B�v ���z�搶�@�u������ł�낤�B�����I�ɂ͎��]�Ԃɏ�邱�Ƃ��\���낤�B�v �@ �@�V���P�W���A�ؓ��g���[�j���O�p�̐��i�P�C�Tkg�j���i�[�X�X�e�[�V����������B �Ȍ�މ@����܂ŁA���n�r�����ł��g���Ɠ��ʁi��S�O���j��a���̃x�b�h�ŗ[�����{�����B �ǂ�ł��������ŏo���������t�Q�B �@�@�u�@�l�Ԃ͊�]���������Ⴍ�A���]�ƂƂ��ɘV���������B�v�@ �@�A�u�@�|���|���v���_�i�A�t���J�E�}�T�C���̐������B�������E�̂�т��̈Ӂj �@ �@�V���Q�O���A�̏d�T�V�C�Rkg�A��p�O�̑̏d�ɉ����B�i�n�O�Œ�̖ڕ����s���j ���z�搶�A�u�n�O�Œ�͂R�`�U�����t����K�v������B�W����t�őމ@�H���̌�͗���a�@���V���֎��X�ʉ@���Ă��炤���ƂɂȂ邾�낤�B�v �x�c�搶�A�u�@���t����s�̒��q�͂ǂ����H�@�������ˁI�v �@�V���Q�R���A�E�r���ؓ����Œ����瑫���オ��Ȃ��B���͂S���ԂقǁA�g�����P�Z�b�g���₵���̂������炵���i������A���ɂ��邱�Ƃ������̂Łj�B �ɂ݂̂��镔���ɃA�C�X�m���Ă�B�ߑO�Ƀ����g�Q�����������������A�摜�m�F�����Ƃ���ُ�͖����Ɠn�ӈ�t����m�炳�ꂽ�B �@�V���Q�S���A���n�r���ŏ��߂āA���t����g���Ă̊K�i���~����K����B  �x�c�搶�A�u�@�n�O�Œ�Ƃ͒����t�������ɂȂ��@�v �x�c�搶�A�u�@�n�O�Œ�Ƃ͒����t�������ɂȂ��@�v���z�搶�A�u�@���ۂ�����Ƒ�ς�����A�n�O�Œ�̃s���ɂ͎��G��ʂ悤�Ɂ@�v���ӁB�@�s���Ƌr�̐ڍ����i���̎ʐ^�j���T�ɂP�x�͏��ŁE�_�������A�K�[�[��ւ��Ă���B �@�V���Q�W���A���n�r����쓇��t�����ɗ���ꂽ�B ���t��ł̐������s�͗ǍD�A�K�i���s���S����Ɍ��ɗ��鎖�ɂȂ����B �@�V���Q�X���A�����ɑ����Ē��J�쏕�����i�Ғł����H�j����f�A�u��ϓ����p�����ꂽ�̂�����A�撣���ĂˁI�v�Ɛ���������ꂽ�B �@�V���R�P���A�x�c�搶�A�u�@�E�r�̎w���A��ɏ�Ɉ�������悤���@�v�ƃA�h�o�C�X��B ���w�͎�p�Ő_�o���ؒf���ꂽ�ׂɁA�e�w�E�l�����w�E���w�͉��ɂ͋Ȃ��邪��ɏグ�邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ��Ă���B �@ �@�W���P���A�쓇��t�����n�r�������āA�u�@�K�i�̉��肪�����s���肾���ꎞ�A��͉\���낤�@�v�ƌ����A���z�搶����́u�@�n�O�Œ���͂�������������߂�̂�����B �W���i���j�ߌォ��P�O���i���j�Ɉꎞ�A��ėǂ��B�v�Ɠ`����ꂽ�B �@���Ƃ��ẮA���Â͎Ă��Ȃ��̂ŁA���@���Ă��Ă����n�r���ȊO�͓��ɂ��邱�Ƃ������Ȃ��Ă������ƁB�����̎���ɒu���Ă�����R�̓��A�����S�z�Ȃ��ƁB ���ɎČ��͓ˑR�傪���Ȃ��Ȃ������Ƃ���m�C���[�[��ԂƂȂ�A�����Đ��b������Ȃɒ�R������A�U���ɏo��Ǝ����ꐶ�����T���Ă���悤���Ƃ����B�E�т��Ђǂ��A���X���������A�H�~�������Ȃ��Ă����ƍȂ��畷���Ă����B �܂��A�Ă̐A�ؔ��̐����͐��������čȂɏd�J�����������ԂŁA�P���������މ@�������Ƃ����C�����������Ȃ��Ă����B �@ �@�W���R���A���z�搶�ɁA�Ȃ̗v�]������@�u�W������P�O���̈ꎞ�A����A���̂܂ܑމ@�Ƃ����Ē����������v���肢���Ă݂��Ƃ���A����ł��ǂ��Ƌ����ꂽ�B �@�W���U���A�S�K�a���������t��ŕ��s���K������B ���z�搶����A�u�@�މ@�������W���̌ߌ�R���A����a�@�O������f����̂��P�P���ŁA�B�c�搶�ւ̏Љ�����p�ӂ���B�v�Ƃ̊m�F����B �@�W���V���A���z�搶�A�u�@�މ@���Ă��O�͏������疳�����Ȃ��B�]�|���Ȃ��悤��������悤�ɁB�v�@ ���w�Ö@�m��T���������A�ؐ���My���t��̒������m�F�E�������Ă��ꂽ�B �@�W���W���i���j���j�A��̏�ł͗��H�A�䕗�P�O�����ڋߒ��ŏ������������B �@�`�킪�}���ɗ��Ă��ꂽ�̂ŗ\���葁���Q���R�O�����މ@�B�i�[�X�X�e�[�V�����ł́A�����q�Ō�t���͂��ߑ����̊Ō�t�̊F����ɏΊ�Ō������A�։z�����ԓ��Œ����ցB �U���P�V���̓��@������T�R���U��ŊO�̋�C���z���B �������e�̃X�X�L��������������Ă����̂ɋ����A�G�߂ƂƂ��ɕς��s�����i�߂Ȃ���A�����ł͓��R��n�����̏��щƂ̕�ɎQ���Ă���A�S�����߂��Ɏ���֒������B
�@ �~�[�^���͊Ԃ��Ȃ����̎�ɏ��A���ɂƂ܂��Ċ�Ԏd���B �i�b�`�����͑����Č��C�Ȃ��A���̊���������茩�ꂸ�A�s�M���H�肩��K���i���p�j������ĐH�ׂ����A�͂Ȃ��A���낤�Ƃ���C�z�i�a�C��������Ȃ��j�B �[�H���H�킩��łȂ��A�Ȃ̎�̏ォ��H�ׂĂ����B �@���߂Ă̎���ł̃V�����[�A���C�ꂪ�����B�����̋����ƁA��ɂ��������܂��ĉ��t�����̂Ƒ䕗�̉e���������Ă��A�����Ċ��������Ė���Ȃ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ɖ߂�
�@����×{�̂��߂̉����Ȃ��B�@ �@�����Ȃ��肭�˂����L���ł��g�����Ԉ֎q�����p�i�X�ɂ������̂Ń����^������B �A�V�����[�����������̂ŁA�z�[���Z���^�[����o�X�|���v�ƃV�����[�����Ď����Ōq���ŗ����̓��ŃV�����[����B �B���ցE�L���̈ꕔ�E�g�C���E���C�������_�����t����B �C�g�C���ƕ��C��̖ؐ��h�A���͂������A�R�[�f�I���h�A�ɕt���ւ���B �D�L���Ƌ�����g�C���Ԃ��i���������镨��\��t����B �B�`�D�͋Ǝ҂Ɉ˗��B �@�V����w�㎕�w�����a�@�i���̂��ύX�ɂȂ����j�ւ̊O����f�́A���̌�A���ʂƂ��ĂX���S���A�P�O���P�U���A�P�Q���P�P���A�P���Q�X���̂S���f�����B�ڐA�������̒�����ƁA�x�ւ̓]�ڂ��������̊m�F�̂��߉E�r�Ƌ����̃����g�Q���B�e�����A���z�搶����f�f���A�n�O�Œ���͂��������f���Ă��������B �@���쑍���a�@�ɂ́A���T�P�j���ɊO����f���āA�n�O�Œ�̃l�W�s���Ƌr���̐ڍ����Ɉُ킪�������A�m�F���Ă��炢���łƃK�[�[�̌��������肢�����B ���z�搶����n���ꂽ�Љ��ƃ����g�Q���ʐ^�����Q���āA�W���P�P���əB�c�搶�̐f�@���A�X�����܂łW��B�B�c�搶������A���H�a�@�֓]���ꂽ�̂ŁA�P�O������͎�ɓ��R�搶�ɂQ���Q���܂łP�W��A�v�Q�U���b�ɂȂ����B �����Ă��P�O���قǂ̋������A����^�N�V�[�Œʂ����B�Ƃɕ������鐶���̒��ł́A�O�̋�C�ɐG���M�d�ȋC���]���̎��ԂƂȂ����B �@���̊ԁA�S�{�̃s���̂�����ԏ�̕G�ɋ߂��s������͏�ɉ��F���`���o�Ă����B ���������Ă�����������ɖ��͖����A�T�Ɉ�x�͎����g�����Ŗ�ƃK�[�[���p�ӂ��Ď蓖�Ă������B �@�Ƃ̊O���ɂ́A���t����g���ĉE�r�͓˂����ɕ����B�r�͂��K�v�Ō��\����B �܂��A���̔N�͐��E�I�Ȉُ�C�ۂŁA���[���b�p�͔M�g�ɏP���A�t�����X�ł͐���l�̎��҂��o��قǂł������̂ɁA���{�͂P�O�N�Ԃ�̗���ł������B �������Ă��䂪�Ƃ̎R�쑐��Ԗɂ͍K�������悤���B �@��Ăɑ����H�͏������������A�~���g�~�ŐϐႪ���Ȃ��������ቺ�낵�̐S�z�������ė×{���̐g�ɂ͗L������B �@�����Ǘ����o���Ȃ�����������  �@���O�ɂ���|���e��������`���E�i���炪��������j���S�ł������A�r�̌�Ƌ����͂��ׂČ��C�������̂ɂ͋������B �@���O�ɂ���|���e��������`���E�i���炪��������j���S�ł������A�r�̌�Ƌ����͂��ׂČ��C�������̂ɂ͋������B�@ �@ �������N�x���ɕ����邩�ǂ����������炸�A�×{���������C�z�ł������̂ŁA�}篁A�ʂɓK�C�҂�T���Ă��炤�ׂ�������ɂ��肢���A�������B�i�X�����j �@ �ق��̃z�[���y�[�W�͌��ꂽ�̂ŁA�C���^�|�l�b�g�ō���ᇁE�A�_�}���`�m�[�}�ׂ��B������ᇂƂ��Ă͂��ƂȂ����^�C�v�i���܂�]�ڂ��Ȃ��H�j�ŁA���ǗႪ���Ȃ��悤���B �����Ĕ��������o���Ȃ��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�Ń��[�J�[�ɒ��ڒ������A�J�X�^�����C�h�łP�V�C���`�t���f�X�N�g�b�v�p�\�R�����w�������i�P�Q�����j�B �p�\�R���\�t�g�⏑�Ђ��C���^�[�l�b�g�V���b�s���O�ŃJ�[�h�x�����ƂȂ����B�@ �P���ɂ�ISDN�����ւ���ADSL�ɉ��������B �@ �����āA�ܕ��������K�ɂ͏オ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B�@���̍����z���āA�����ŏ������Ă��A�~�g�����g�C���ƕ��C���������ł���A�o���A�t���[�̉Ƃ���邱�Ƃɂ����B �H�̂����ɐ}�ʂ��o���A���N�t�ɂ͍H���ɓ���A�Ăɂ͊����\��Ƃ����v�悪�o���オ�����B �i�����P�U�N�R���Q���A�����_��j �@���́A���z�搶�ɂ��b���ĂȂ��������A�H����~�ւƊ����Ȃ钆�łP�O���N�Ԃ�Łu���v���o���B ���j�Œɂ݂͖������r�֎��̏o�����������B �Ƃ��Â��\���̂܂܂ŁA���C��ɒE�ߏꂪ�����A�����̃V�����[���A�g�[�̖����L���̈ꕔ�ŗ��ɂȂ��ĉE���Ƀ|���܂����Ԃ��ăe�[�v�Ŏ~�߂Ă��痁���ɓ���B �������������ƎԈ֎q�̐��������̌������H �@�P�O���P�U���̑�w�a�@�O����f�B�U���R�O���̎�p����R���������o�߂����̂őn�O�Œ���͂����Ă��炦�邩�Ɗ��҂��Ă������A�u���̍��̒���������܂ЂƂv�Ƃ������ƂŁA�p�����ď�Ԃ����邱�ƂɂȂ�B �@����̎�f�܂Ŋ��Ԃ��������̂ŁA�ȂɎ菕�����Ă��炢�Ȃ���A�R�쑐�̐A�ւ��������B �P�����E�L���J�A�T�N���\�E�A�G�r�l�A�R�V���N���N�A�V���l�A�I�C�A�ኄ���A�ȂǕ��u����Η��N�ɂ͎͌����鋰��̂�����̂�����I��ŁB ���s���āA�A���~�I�i�P�W�Ocm�Q�i�j�Q��������̘L���ɓ���A�ቺ�ɂ������Ȃ����A������ׂ��B�Ԗ̔����́A����~�͂��ɗ����Ǝ҂ɂ��肢���āA��p�̈͂�������Ĕ����ړ����Ă�������B �r�̌�Ƌ����͒r�̏�ɖ؍ނ��ڂ��A���߂ĊO�ʼnz�~�����Ă݂��B �@�P�Q���P�P���A�z�~�̏������ς܂��A���ł����@��p���o����Ƃ�����ԂŗՂ�w�a�@�O����f�B���̈ӋC���݂Ƃ͗����ɁA���z�搶�͋ɂ߂ĐT�d�ł������B ��p���̂��̂́A���Ԃ������炸����Ȃ��Ƃ���ꂽ���A�u�܂��A���̍��̒����ɕs���������v�@�Ƃ��āA���̎�f�����P���Q�X���ɂ��A���̌��ʂ�f�ē��@�Ƃ������ƂɂȂ����B ��p��T�����ȏ�o�߂��Ă���A�܂����Ƃ����v�������������A�u�l���͑҂����v�Ǝv�������B �@ �@�Q�O�O�S�i�����P�U�j�N�@�P���Q�X���A��w�a�@�O������f�B�V�����o�߂��Ă悤�₭�҂��ɑ҂������@�̎�z�ɂ͂��ꂽ�B�@���t�A�A�A�S�d�}�A�x�@�\�A�Ȃǂ̏���������B �@�Q���R���A�����ȊO������f����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Q���U���i���j���j�A�V����w�㎕�w�����a�@�����@�B�O����@���Ɠ����a���ŁA�a���������S�P�U�����ł������B���������a���ƊŌ�t�̊F����Ƃ̍ĉ�ł������B ����̒S���̓x�e������Hi�Ō�t�Ń����o�[�͑O��Ƃ͈قȂ�`�[�������A�������M�S�ɐ��b���Ē������B �̏d�U�Skg�i�W���W���މ@���T�Wkg����A�X���ɂ͂U�Qkg�A����ɑ����āj�Ƒ��������B �^���ʂ�������ɉh�{���l�������ʂł���B�@�̉��R�U�C�U�x�A�����P�Q�O�|�V�O�B �[���A��p���Ō�t�i�j���j���������A��p�̐��������Ă��ꂽ�B �x�c�搶���Ⴂ�ڗǁE�e�r����t�i�����o�[���B�쓇��t�̓A�����J�֗��w�A�n�ӁE�h�X��t�͂��ꂼ��Ⴄ����̌��C�Ɉړ��H�j�Ƌ��ɉ�f���āA����̎�p�ɂ��Đ��������ꂽ�B �@�Q���V���A�Ȃ����Ȃ��āA���z�搶�����u�n�O�Œ蔲���A�M�u�X�Œ�v��p�̐������A���ӏ��ɃT�C�������B �@�@�S�g�������s���A����̍��ڍ����ɂ������������A�n�O�Œ�̋��������B �@�A������́A������v���X�`�b�N����������t����B �@�B�����ǂ�A��p����̍��܁A�x�[�Ǔ��͋H�ƍl����B �@�C���������ɔ�ׁA�C���݂̂ł͏\���ɋ����Ƃ͂����Ȃ��B �@�@�@��������܂̉\���͂���A���̓s�x�Ή�����B �@�D�ǂ����Ă��ڐA���̖������s�\���Ȃ�A������x�t�������B�i��p�̂�蒼���H�j �@��A�����Ȃ̈�t����f�ɗ����A�������ӏ��ɃT�C������B  �@�Q���X���i���j���j�A��p���BT���тƕa�߂ɒ��ւ��A�W���Q�O���ɎԈ֎q�Ŏ�p���ֈړ��B �@�Q���X���i���j���j�A��p���BT���тƕa�߂ɒ��ւ��A�W���Q�O���ɎԈ֎q�Ŏ�p���ֈړ��B�_�f�z���Ŗ����������A��͋L�����ɂ݂��S���Ȃ��B���ŌĂыN�������܂ł����Ƃ����Ԃ̊����ŁA��p�͂P�T���ʂŐ��������Ɠ`����ꂽ�B �V�����]�ŁA�Œ�����菜���ꂽ�i���̉摜�j�B �P�O���ɂ̓x�b�h�ɐQ���܂ܕa���ɋA�����B �@�Ɏ_�f�̊��i�[���܂Łj�A�r�ɓ_�H�i�R���܂͂S���ԁj�A�E�r�̓M�u�X��������r���̏�ɏ悹���Ă���B �w�悪�����A�r���㉺�ł���B����̃s���i�n�O�Œ�́j�Ղ��r���r���i���̒ɂ݂͗����ɂ͉����j����B �����ɂ͑������h�����Č������悭�����B�����t����ꂽ�i�����܂Łj�B �P�P���߁A�x�c�A���z�A�ڗǁA�e�r�̂S���̐搶������f�ɗ����A�u�@�ߌ�ɂ͐�������ł��ǂ��A�����ɂ͎Ԉ֎q���\���낤�B�v�ƌ���ꂽ�B�̉��R�U�C�W�x�A�����P�Q�O�|�V�O�B �@ �@�Q���P�O���A���A�̌��E�����^�I���Őg�̐@���B���H�̓x�b�h��ŁA���H�͎Ԉ֎q�ňړ����ĐH�����Ƃ�B �[�����t��ŘL��������ƁA�ז��������n�O�Œ�̋�������Ȃ��ċɂ߂ĉ����B �@�Q���P�R���A�̏d�U�Q�C�Tkg�B���`�O�ȊO���Ŗx�c�搶�w���̂��ƂŁA�ƎҁiA�`�����쏊�j�ɂ������̌^����������B�@���̌�x�c�搶����M�u�X�����������Ē����A���܂ł��X�����ɂȂ����B(�E�ʐ^)  �@�Q���P�V���A�V�����[�𗁂т�B�U�N�O�ɑ��Ɛ��𑗂�o�����w���S�C�̋��w�N��i�R�N�O�܂ŋΖ����Ă������Z�ōŌ�ɒS�C�������w�N�̉�j�̈ē��n�K�L���͂����B�m�点�ĂȂ������̂ŕa�C�̎��������A�މ@�ł����琥��o�Ȃ������Ǝ莆���������B �@�Q���P�V���A�V�����[�𗁂т�B�U�N�O�ɑ��Ɛ��𑗂�o�����w���S�C�̋��w�N��i�R�N�O�܂ŋΖ����Ă������Z�ōŌ�ɒS�C�������w�N�̉�j�̈ē��n�K�L���͂����B�m�点�ĂȂ������̂ŕa�C�̎��������A�މ@�ł����琥��o�Ȃ������Ǝ莆���������B�@�Q���P�X���A�a���̖ʒk���ŁA���z�搶���������g�Q���ʐ^�R�����f���Ă��炢�A������f�W�J���ŎB�e�����B ���̃z�[���y�[�W�ɍڂ���ړI�ŁA������ʂ��ĕa�@���������J���\�������o���ċ��������ł̎��ł���B �@�Q���Q�O���A���`�O�ȊO���ŁA�Ǝ҂�A��������u����v�i���ʐ^�j��  �t�����B���ۂ������̂Ŏs�����ɒ�o����ؖ�����x�c�搶�ɏ����Ă����������B �t�����B���ۂ������̂Ŏs�����ɒ�o����ؖ�����x�c�搶�ɏ����Ă����������B����̓v���X�`�b�N���ŁA�^��肵�č�����̂ő��ɂ҂�����ŁA�����鏊���ɂ݂��S�����������B �O������Ƃ��́A����𒅂����܂܁i���ʂ̌C�͗����Ȃ��̂Łj���p�̌C�𗚂��B �����ɂ��މ@���ėǂ��ƌ����A�����������@���ă��n�r���������Ɛ\���o�Ă݂����A�u�@���̕K�v�͖����B�މ@���ĉƂɋA��̂���Ԃ̃��n�r���ɂȂ�B�v�@�Ƙb���ꂽ�B �a���܂ő����t���ď��t��ŕ����ċA��A�a�����������ĉ�����B�y���y�ɕ�����B �Ԉ֎q�łȂ��A����t�E���t��t�ł͂��邪�X�����Ԃ�Ɏ����̑��ŕ������B�@�v�킸�S�̒��Ŗ��@�_(^o^)�^�I �ߌ�A�e�r��t���������A�n�O�Œ���͂������s���Ղ��㉺�S�ӏ����������B �������玆�o���\�R��\���ē������\�ƂȂ����B ���̓��͈�������炵�����V�ŁA�ō��C���P�O�x�ŕ��N��T�x�������Ēg���������B �@�Q���Q�P���i�y�j���j�A�މ@�̓������V�B�@ �̏d�U�Q�C�Qkg�i����̌��ʖڕW�͂T�U�C�Tkg���j �X���ɐ��z�搶����f�ɗ���ꂽ�̂ŁA�މ@�̈��A������B �`�킪�}���ɗ��Ă���A�ꏏ�ɂP�Q�K�ŋL�O�H�������Ă���P�Q�����މ@�����B ���x���H���Ŕz�V���ŖZ�����AO�Ō�t�P�l�ɂ�����Ȃ������B ���@���Ԃ��Z���������̂ŁA����ɋA��ƎČ��̃i�c������U���Ċ�т�\���B �҂����������������A�W�����U��ŗ����Ɏ�܂ŐZ����B�g�̂̐c�܂ʼn��܂�A�����o�銾�ƂƂ��ɁA�K�������ݒ��߂��@(^^��B
�@�Q���Q�Q���A�����^���̎Ԉ֎q�͕ԋp���A�Ƃ̒��Ǝ��͂����H�����t����g���ĉE����˂��ĕ����B �����[���R�̕��Ƌ�C�̓����������Ȃ���E�E�E �@�Q���Q�S���A�މ@������Ƃ��āA�a�C�����������ߏ��̊F����ƒ���������̂���ɂ͒��ڂ���Ɏf���A�����̐e�ʂȂǂւ͗X���Ō��������B �@�Q���Q�V���A��w�a�@���`�O�ȊO����\���f�B���t����g���Ȃ���A���߂č����o�X�ɏ�����B ��Ԍ��̃X�e�b�v���������A���~���T�d�ɂ����B �����g�Q���B�e�A�x�c�搶�ɂ��摜�f�f�Ƒ���̓_�������Ă��������A�u���t��Ȃ��ł̕��s�������v���ꂽ�B�A��͐�ɂȂ�A�o�X��łQ�O���]��҂������A�����̌����Ő���̒��ł��s�v�c�ȂقNJ����͊����Ȃ������B �@�Q���Q�W���A�ߑO�ɁA�i�b�`�����ƈꏏ�ɎU���i�O�N�̂T�����ȗ��̂��Ɓj�A�Q�l�ƂP�C�Œ����������B��Ȃ��ŏ����r�b�R�������Ȃ���A�����ň�����A���i�͍Ȃ���������C���ɕ����i�c�͎����`���`�����Ȃ��瑬�x�����킹�Ă����������B �@��U���A����������Ɂu���w�N��v�ɏo�ȁB�ސE���̑��ʉ�ȗ��A�Q���҂X���ŋ��������߂Ȃ���y�����ЂƎ����߂����B�v���������A�މ@�j���̉ԑ��܂ŗp�ӂ���ċ��k���A�L��v���ň�t�ɂȂ����B  �@�Q���Q�X���͉J�V�Ŋ����O�̎U���͏o�����A�މ@������������Ă���g���݂̂ƂȂ����B �@�Q���Q�X���͉J�V�Ŋ����O�̎U���͏o�����A�މ@������������Ă���g���݂̂ƂȂ����B���̓����玤�ɂ��o�����~�܂�A�Ȍ�P�����Ǐ����B ���@���͒g�����̂Ŗ���g��Ȃ������̂ɏǏy���Ȃ�A�މ@���������ƕ������Ƃ��o����悤�ɂȂ����玤���������悤���B �@�R���P���A��A�E�������̓y���܂��ƊO���̋ؓ��H���ɂ��đ̏d���|����ꂸ�A���t��Ȃ��ł͕����Ȃ��Ȃ����B �}�ɕ����߂����悤�ŁA�P�T�Ԃقǎ�����ӂ̏��t����s�݂̂Ƃ���B �@�R���W���A���͎���e�̕������A�[���ɂ͍Ȃ����[�h�������U���ɓ��s���A���t��ŕ����B �߂������g��̓y��Q�`�Rkm���P���Ԉʂʼn���i�E�̎ʐ^�j�B ���̃p�^�[�����P�T�ԑ�����B �@����̉E���͂����Ƃ������Ȃ��Ă���A�����̌C�������Ƃ̍����C�i�C������ł͓K���Ȃ̂������A�ʔ̂łUcm�A�b�v�V���[�Y���w�������j�ɑւ���������Ղ��Ȃ����B �@�R���P�T���A���������t��Ȃ��Ŏ���e����������B ����̂ݕt���Đ��P�Om���R�`�U�����A���̓��̒��q�����ĉ������A�Ȍ�p�����Ă���B �[���̌��Ƃ̎U���͏��t��œ��s����B �@�܂��A�����ɔ����ؓ����t���Ă����̂��낤�A����͋r����ߕt���߂��銴���Ȃ̂ŁA�O��������̂ݎ��t�������Ƃɂ����B �@�R���Q�O������A�J�V�ȊO�͖����������A�Ȃɏ������Ȃ���A�R���I���Ɣ��ړ����n�߂�B ��������O�̒I�ցA��̐�͂��┫�A����p�̈͂��̒�����O�ցA�����E���e����I�ցB ���������ĕ�������A�W���E���Ő�������������o����悤�ɂȂ��ė����B �@���łɕ�������R�V�m�R�o�C���̉Ԃ͏I���A�J�Ԓ��̐ኄ�������̏�ɂ����ƕ��B ���A���̃J�^�N�����Q�݂������A�{�P���J�Ԃ��n�߂Ă����B �@�@�@�@�@-�@-�@-�@---------------�@-�@�����܂ŁA�@�Q�O�O�S�i�����P�U�j�N�R���R�O���A�L�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȍサ�炭�i�Q�O�O�V�N�Q���܂Łj���̃y�[�W�̋L�q���x��-�@-- �@ �@�S���R���A�{��P�����E�{���Q�V����@�v���c�ށB �@�S���͂T�����琰�V�������A�C���̍������������A�r�̒��q���ǂ��B���̊J�Ԃ���N��葁���A�����[���̌��U���ɂ͏��t���˂��Ĉꏏ�ɏo�����A�����]�ʼnԌ����ł����B ���ӂ����A���ւ̐�������A�Ȃ̎菕�������ł���悤�ɂȂ�A�����v�͂V�炩��P�������L�^�����B ���N�����ɂ́A�x�b�h��łR�O�`�S�O���������X�g���b�`��̑�������B �ؓ��g���[�j���O�͖����̉^���ʂʼn������A�E����ɂ��T�O�Og�̃��X�g�o���h���Q�{�����ĂPkg�܂ŕ��ׂ��|������悤�ɂȂ����B. �܂��A�����̎p���ŏo����@����g�����T�C�N���^���ӂP�T�����������B  �S���P�S���ɂ��̏d���Q���U�Okg�܂Ō��ʁi2,2kg�j�ł����B �S���P�S���ɂ��̏d���Q���U�Okg�܂Ō��ʁi2,2kg�j�ł����B�@�S���P�T���A������z�ׂ̈̍H�����n�܂�B ���z�������ɍ��̉ƂŐ������Ȃ���A�Ƃ̈ꕔ�����A���ƉԒd��ׂ��ĕ��������Ă�B��^�̃����{�������ċ͂��R���ԂʼnƂ̈ꕔ���A�r����̊��x��グ�����n�����B �傫�Ȓ���P�O�{���́i�����Ǝ҂Ɉ˗��j���A���Ƃ����A���͎����ňړ��������A���̋r�ł͏������Ԃɍ���Ȃ��B  �ڐA�������������̍앨�i�A�X�p���K�X�A�j���A�A�V�^�o�A�H�p�e�A�C�`�S�Ȃǂ̏h���ށj�ƉԒd�̑��ԁi�V�����A�j�[�A�z�^���u�N���A���P�����A�e�틅���ނȂǁj�͑S��������Ő��n����Ă��܂����B �ڐA�������������̍앨�i�A�X�p���K�X�A�j���A�A�V�^�o�A�H�p�e�A�C�`�S�Ȃǂ̏h���ށj�ƉԒd�̑��ԁi�V�����A�j�[�A�z�^���u�N���A���P�����A�e�틅���ނȂǁj�͑S��������Ő��n����Ă��܂����B�r�̌�V�C�͖Ⴂ�肪�����ď��������B �@���̓��[���A���Ƃ̎U��������l�ŏ��t��Ȃ��Ŏ��݂�B �P���ԗ]��A�Č��̃i�c�����̕����ɍ��킹�Ă����̂ŁA��Ȃ��o�����B �Ȍ�A���͍Ȃ����ƎU���ɏo�āA���̓W���E���Ŕ��ɐ���������A�[���͍Ȃ��Ǝ��ɐ�O���A�������ƎU���ɏo�āA���̌�ɔ��̐���������  �p�^�[���ƂȂ����B �p�^�[���ƂȂ����B�@�S���Q�O���A�O�����J�̂��ߐ�����s�v�Ȃ̂ŁA���̌��U���ɏ��t���œ��s���Ă݂��B �C�����Ⴍ�r���ɂ��B���ʂP���ԗ]�̃R�[�X�������ł������Q���ԂقNJ|���ĕ������B�������ŕ����v�͂T����������������������B �V���l�A�I�C��^�c�^�\�E�͉Ԃ��I���A�ˉB�V���E�}�E�����E�~�ԓ��������J�Ԓ��B�e��̒ւ����X�ԊJ���A�G�r�l�B���Ԍs���グ�Ă����B ���̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� |
�`�@������z�H���@�ˁ@�V���ւ̈��z���@�` �@ |
 �@�Q�O�O�S�N�S���Q�P���A�n�����B�@�ߌォ���b�H�����n�܂����B �@�Q�O�O�S�N�S���Q�P���A�n�����B�@�ߌォ���b�H�����n�܂����B�n�k�ɋ����x�^��b�Ƃ��A�Q�S���Ԋ��C�V�X�e���ŏ����ɂ���C���z����������Ƃ����B �@�S���Q�R���A�Q�����Ԃ�ő�w�a�@���`�O�ȊO����f�B�o�ߗǍD�B �@�S���R�O���`�T���R���A�A�x�ɒ��j�����s����A�Ȃ��A�[���̌��U�����ꏏ�ɂ����B�C���ǂ�������L������r�ɒɂ݂��o��B  �@�T���P�Q���A�㓏�����s��ꂽ�B�@�T���̒����̍~���ʂ͕��N�̂Q�{�ƂȂ�ُ�ȋC�z�B �@�T���P�Q���A�㓏�����s��ꂽ�B�@�T���̒����̍~���ʂ͕��N�̂Q�{�ƂȂ�ُ�ȋC�z�B�@�U���W���A���~�B�@�J�V�ƒቷ�́A�U�����̋r�ɂ������N�����A�����v�łS��  �`�T����Ə��ȖڂƂȂ����B�@�̏d�T�W�C�Tkg�B �`�T����Ə��ȖڂƂȂ����B�@�̏d�T�W�C�Tkg�B�@�U���P�W���A�V��a�@�O����f�̓��B �����o�X���~��ĕ������߁A�r���ɂ��B �����p�̑��ꑕ�����邽�߉E�r�̑��牺���^��肵���B �@ �@�U���Q�O���A���߂�����𒅂��Ȃ��ʼn��O������B ������ɂP�A�Tkg�̐��A�E����ɂ͂T�O�Og�̃x���g���Q�{�������Č��݂ɋr�グ�g�����P�O�����P���Q����B  �@�U���Q�T���A�V��a�@�O����f�B �@�U���Q�T���A�V��a�@�O����f�B�����p�̑��ꑕ��o�����̂Ŏ��t���Ă݂�B ���������ʓI�ɁA���̑���͂��܂�g���邱�Ƃ����������B �r�̒ɂ݂̂��߁A�x�c�搶�������Q��ޏ������Ă����������B ���Ɨ[�H����ɂݎ~�߈��ݖ����A����������z����\��B�Ȍ㖈���g�p���邱�ƂɂȂ����B �@�U���R�O���A�O�ǍH���n�܂�B�[���̌��Ƃ̎U���Ɣ��̐����莞���������  ���A���͑�����ōs������B ���A���͑�����ōs������B�@ �@�V���T���A�䕗����̒�C�������{�C��ʉ߂��A�t�F�[���̔M�����P���R�W�A�R���̖ҏ��ƂȂ�B �V���̒����́A�R�T���ȏオ�T���Ԃ�����A���ϋC�������������B �W������̂��A�����J�V���q�g�����唭�����āA��̗t���H�Q����A�������ގ��ő�ςł����B  �@ �@�@�V���P�R���A�O�邩��̋����J�ŋL�^�I���J�i�V�A�P�R���Q�j�ƂȂ�A�䂪�Ƃł��M�ы�����������P�Ocm���Z���i���܂łɖ������Ƃł������j�����B ��̔����ꎞ���v�������ꂽ���̂��������B �@�V���P�X���A�C�̓��B���݉�Ђ̎�O�S�l�ɗ���ŁA���d�E�①�ɁE�x�b�h�E�\�t�@�[�E�K���X�t�����I�ȂǑ�^�Ƌ���Q���ԗ]��ň����z�����B���ؑ��ꉮ����s�v�Ȃ��̂͏o���邾  ���������A�p�\�R���E�ߗށE�䏊�p�i�Ȃǎ��ƍȂʼn^�ׂ���̂��Q��������ʼn^��ŁA�܂��������̐V���Ɉڂ����B ���������A�p�\�R���E�ߗށE�䏊�p�i�Ȃǎ��ƍȂʼn^�ׂ���̂��Q��������ʼn^��ŁA�܂��������̐V���Ɉڂ����B�@�V���Q�Q���A�V��a�@�O������f���A�ɂݎ~�ߖ�̏���Ⳃ�Ղ����B  �@�V���Q�R���`�Q�W���A���ؑ��ꉮ�������A �@�V���Q�R���`�Q�W���A���ؑ��ꉮ�������A�Q�X��������S���u���b�N���i�P�K�͕��u�A���]�ԁE���̃T�[�N���u����ƔM�ы����牷���A�Q�K�͒��j�����������g���������Ǝ��̏����{�u����Œz�Q�U�N�j�̉�̂��s���A �@ �W���T���ɉ�̏�����Ƃ����ׂďI�������B  ���̊ԁA�Q�S���i�y�j�`�Q�T���i���j�̉�̋Ǝ҂��x�݂̓����A�Ȃƈꏏ�ɓS���u���b�N���̂P�K���牀�|�p�y�␅���ȂǁA�Q�K���珑�I�Ɩ{���^�яo���ĐV���̏��ɂɔ[�߂�B ���̊ԁA�Q�S���i�y�j�`�Q�T���i���j�̉�̋Ǝ҂��x�݂̓����A�Ȃƈꏏ�ɓS���u���b�N���̂P�K���牀�|�p�y�␅���ȂǁA�Q�K���珑�I�Ɩ{���^�яo���ĐV���̏��ɂɔ[�߂�B�~�n���ňړ������͒Z���̂����A���I������o���������̗��Əd���͑�ςȂ����ł������B �@ ���Ԃɗ]�T�����A���S�ɖ����������Ĕ�J���ނ��A�̏d�T�Vkg�ƌ��ʂȂ�B �@�V���Q�W���A���̐����ƉԂ̎ʐ^�B�e�����Ȃ̂ɁA�E�r�͋ؓ��ɁA���ɒ����i�ӂ���͂��j���ɂ��B
�@�W���P���A�ō��C���R�V�A�Q���B�M���B�̏d�T�U�A�Vkg�B������A���U���Ƃ��ɑ����t�������r���ɂ��B�����A���i���ˁj�Ƃ��ɔ��ɒɂ��B �����ɂ͌��Ƃ̎U�����o���Ȃ��Ȃ�A�X�ɐ�������o���Ȃ���ԂŁA�ɂݎ~�ߖ�������Ȃ��Ȃ荡���ōň�(�E_�E;)�ƂȂ�B �@�W���U���A�����x�b�h��Ń|�L���Ɖ������ĉE�r�Ɍ��ɂ�����B�������ƒɂ����A����ʼn������ăW�b�g���Ă���ƊԂ��Ȃ��ɂ݂����܂��B�Ȃ͎��X�A�Q���ɑ������i�j�鎖������̂ŁA��ꂩ��ؓ����z�������̂��Ǝv�����̂ł���B �E�r�𒅂��Ȃ��Ă������オ��ƒɂ��̂ŐQ�Ă������A�g�C���s�����K������������H�ł���Ƃ̎v���ł�����(*_*;�B�[���܂��|�L���Ɖ��������B �@ �@�W���V���i�y�j���A���z���\��ւ��悤�Ƃ������A�r���_�����ƋȂ������B�������I(+_+)�@�����ɒ������ɂ̓v���X�`�b�N����āA�����ɂ͑������Ȃ��Ȃ��Ă����i��ꂽ�j�̂Ń{�[�����ĂĕR�Ŕ����ČŒ肵���B �f�Â��Ă�������a�@���`�O�Ȃ͉^�����x�f���ŁA�������s���̒��������a�@���Љ�ꂽ�B �ߑO�P�O���A�����g�Q���B�e�����āA����t����ڐA�����Q�{�Ƃ��܂�Ă��邱�Ƃ��m�F����A ���T�̂P�O���Ηj���i��ᇊO���̓��j�ɑ�w�a�@�ɂ����悤�Љ���Ղ����B�[���������J�ƂȂ����B ���̊ԁA����ŌŒ肵�Ă���ƒɂ݂͖����A���t��ƍ��r�ŕ����邪�P�����Ƃɂ���B �Ȍ�A���ӂ̌��Ƃ̎U�����A�ؔ��̐�������A�܂��A���ׂčȂɂ���Ă��炤���ƂɂȂ��Ă��܂��\����Ȃ��v���B �V��a�@���`�O�Ȉ�ǂɓd�b���āA���z�搶�ւ̃����A�������肢�����B �@�W���P�O���A�`��̏�p�Ԃő����Ă��炢�A�V����w�㎕�w�����a�@���`�O�ȊO������f����B�����g�Q���B�e���Đ��z�搶�̐f�@����B �ڐA�C���̔�J�����B�u����ȏꍇ�͓��j���ł���w�a�@�ɗ��Ȃ����B�J�~���āA�n�ł܂�̌��t�̂悤�ɁA��������v�ɂȂ���B�v�ƌ���ꂽ�B �O�Q��Ɠ������ٕa���S�O�V���������@�i�f�Ìv�揑�ł͂Q�`�R�T�Ԃ̗\��j�B �a������������Ƃ������āA�S���̊Ō�t����̊�Ԃ�͑��������A�����b�ɂȂ����F����ɏo��ĉ������������B�@�̉��R�U�A�U���E�����P�P�W�|�U�T�B �@�ߌ�Q���S�O�������琶�z�搶�ƎႢ�����t�i�����j�ƂŁA�a���̏��u���ɂ��G��܂ŃM�v�X�������ČŒ�����B �����Ƀ����g�Q���B�e���āA�܂ꂽ�Q�{�̈ڐA�C���̐ڍ������m�F�B�u�@�P�O�O�_���_�ł͂Ȃ��̂ŁA�������H���܂��@�v�ƌ����A�M�v�X�̈ꕔ�ɐ�ڂ����Ĕ��������A�ēx�����g�Q���B�e�����ĂS���Q�O�����ɏI�������B �@�W���P�P���A�X���R�O���A���z�搶������E�����t�ƈꏏ�ɉ�f�ɗ���� �u�@�P�������炢�M�v�X�������ق����ǂ����낤�B���̌�͑����ɐ�ւ���B�ʉ@�ł��邩�ȁH �A��������܂������Ȃ����́A�����Ȃǂ��ڐA���ĕ⋭�������ƂɂȂ�v�ƌ���ꂽ�B �P�O���R�O�����z�搶�Ɛ����t���A�M�v�X�̂܂܉E�r���˂���悤���M�v�X�̑���ɒlj����H���{���Ă��ꂽ�B �@�W���P�Q���A�P�P���������n�r���J�n�A�]�����s����ɑ����ĐV�l�̒j�����w�Ö@�m�n���S���B���̋ؗ̓e�X�g���A���s�_���g�����E�r�R���̂P�d�̊��o�����ށB �̏d�T�Vkg�łP�Vkg�ʉd����悤�ɂ��āA���t����g���ĕ����B �ߌ�ɉE�r���r�j�[���܂ŕG��܂ŕ����ăV�����[���g���B�P�T�ԂԂ�ŋC���u���B �@�W���P�R���A�A�e�l�I�����s�b�N�J���B�ߌナ�n�r���A�R���̂P�d�ł̕��ʕ��s�ɉ����ĊK�i���~���J��Ԃ��B�@���܂Ō������Ƃ������������~�̕�Q����Ȃƒ��j�v�w�ɑ������B �@�W���P�S���A���z�搶�����A�u�Q�T�Ԃőމ@���A�O���łQ�`�R�T�ԗl�q�����悤�B���̊ԂɃM�v�X���ɂ�ł�����ăM�v�X����B�v �@�W���P�U���i���j�j�A���W���߂��ɗ��搶����f�B�x�c�搶�ɂ́u�r���g���߂��܂����ˁB���܉ӏ���������������v�ɂȂ邩��E�E�v�Ɨ�܂���A���z�搶����́u�މ@�͍��T��t�ŁA�����͐��j�����ł��ǂ����ȁB�v�Ƃ���ꂽ�B ���̌�̃��n�r���ŁA�u���t����s�͕��ʁE�K�i�Ƃ��ɖ��Ȃ��A�މ@���\�v�Ɣ��f���ꂽ�B �@�W���P�V���A�ߑO���n�r���A�ߌヌ���g�Q���B�e�B�S�������z�搶���������u�a�����s�����č����Ă���̂ŁA�����ߑO���ɑމ@���Ăق����v�Ƃ����A���������B �@ �@�W���P�W���A���n�r����A�ؑ��搶�i���n�r������̈�t�j�̖�f���A���͎��Ò��Ȃ̂Ŗ��������A �r�̏�Ԃ��Œ肵����A��Q�Ҏ蒠�̐\����������ǂ����Ɛ��������B �x�c�E���z���搶�ƎႢ��t�Q�����������A�u�@�M�v�X�͂S�O���ʁA�X���Q�O�����܂Œ����鎖�ɂȂ�ł��傤�B���͂W���R�P���i�j��ᇊO������f����悤�ɁB�v�Ƙb����A�މ@�̈��A�������B �@�P�P���߂��A�w���i�Ō�t���j����Ɉ��A���ĕa������ɂ��A�Q�`�R�T�Ԃ̓��@�\��ł��������}篂X���ڂőމ@�ƂȂ����B  �@�W���P�X���ȍ~�A����×{���A���Ƃ̎U�����o���Ȃ��̂ŁA�������ł͂Ȃ��Č��̉Ĕ�����莞�Ԏ����\�t�@�[�ŕ��������āA�I�����s�b�N���Z�Ȃǂ��ꏏ�Ɍ���悤�ɂȂ����B �@�W���P�X���ȍ~�A����×{���A���Ƃ̎U�����o���Ȃ��̂ŁA�������ł͂Ȃ��Č��̉Ĕ�����莞�Ԏ����\�t�@�[�ŕ��������āA�I�����s�b�N���Z�Ȃǂ��ꏏ�Ɍ���悤�ɂȂ����B�@���z�H���́A�O�\�H���Ƃ��Ė和�ƃu���b�N����肪�قڏI�����B �傩�猺�ւ܂ł̒ʘH�ƁA�����̕��u�ɂ��闠���ւ��玩�]�Ԃ�Ԉ֎q���o����悤�Ɍ��֑O�܂ŃX���[�v������R���N���[�g�H�����Q�V���܂łɏI���B �@�W���Q�X���A�e�l�I�����s�b�N���B���{�̓��_���R�V�Ŏj��ő��L�^�Ȃ�B �@�W���R�P���A�V��a�@�O����f�̓��B�`������Ƃ����Z�Ȃ̂ŁA�����^�N�V�[�𗊂�(����X���P�S���A�P�O���P���ƂP�O���̌v�S��)���Ƃɂ����B�䕗�P�U���̉e���ŕ��J���ꎞ�����������A�������H���g�������Ƃ���P���Ԃقǂő���͂R���T��~�ł������B �����g�Q���B�e�̌��ʁA�u���̐ڍ��͗ǍD�v�Ƃ̐f�f�ł������B  �@�X���R���A�쑤�ɛ��i�Ђ����j������H������������B �@�X���P�O���A���֑O�̃^�C���\��ƛ����̃R���N���[�g��h�肪�I�����A�悤�₭�V�������������B  ���ւɂ͕��P�Q�Ocm�ƂX�Ocm�̐������Z�b�g�����������̂����A�Ƃ肠�����������S�̂U�Ocm�����ŃK�}���B ���ւɂ͕��P�Q�Ocm�ƂX�Ocm�̐������Z�b�g�����������̂����A�Ƃ肠�����������S�̂U�Ocm�����ŃK�}���B�@�X���P�X���A���j�����s�̏����ƌ��� �i�P�O���R�P���Ɏ���\��j�B ���l�Ɨ��e�U���������ʼn�H������ł��������A����Ȃ��玄�͍s�����Ƃ��o�����A�Ȃɑ�\���ď㋞���Ă�������B �@�P�O���P���A�@�V��a�@�O����f�B�Ǝ҂�A���M�v�X����苎���āA�V�����������邽�߂��^��������A���̌�A�x�c�搶���M�v�X��G�����犪�������Ă��ꂽ�B �G���Ȃ�����Ɗy�ɂȂ�̂ł��肪���������B�����������ɂ͕G��̋ؓ����M���ɂ��Ȃ�A����Ăė⎼�z�B�@�������̂͏������I�I �@�P�O���V���A�V��a�@�O������f���A���������V��������𒅂���B ����Ŋ��S���M�v�X�ƃT���i���ł��B�@�ȑO�̂��̂Ə����Ⴂ�����Ƀl�W�����Ă��Ċp�x�̔��������o���A���z�搶(�j�I�������ɏ��i)�ɂ��f�Ă��炢�A����𒅂����܂܂Ń����g�Q���B�e�����ă`�F�b�N�����B �^�N�V�[�ł̒ʉ@���I�����A����ł������Ɠ��镗�C�̗ǂ����āX�m�F�B(^o^) �W���P�O������T�X���ԃM�v�X�������ꂽ�r�́A�C�i�����j���Q�`�R�������Đ������ƂɂȂ����B ��������G�����g�����������n�߂�B �@�P�O���P�Q���A���t���˂��Ȃ�����[���̌��U���ɓ��s�B�����X�ŎU�����ăX�b�L������B �@�P�O���P�V���A���m���I�������t��g���ē��[���ցB �@�P�O���Q�O���A�䕗�Q�R���ɂ�蕽���ő�̔�Q���o��B�����ł��P�������J�������U�����o���Ȃ������B�@���̔N�U�������v�P�O���̑啗�����{�ɏ㗤�i�ߋ��ő��j�����B ���̃y�[�W�̐擪�ɖ߂� �@ |
�`�@���R�ЊQ�@(��n�k�E����)�@�����z���ā@�` |
| �@�Q�O�O�S�N�P�O���Q�R���A�[�H�O�̂T���T�U���B �@�V�������z�n����k���Ƃ���M�U�A�W�̒n�k�������B  �@������k�x�V�A����J���k�x�U���A�����͐k�x�U���ł������B �@������k�x�V�A����J���k�x�U���A�����͐k�x�U���ł������B���̎��Ȃ͗[�H�̏������ŁA���͋��Ԃ̃\�t�@�[�ŎČ��̉Ĕ�������ăe���r�����Ă��܂����B �c�h��������ĕ��������h�ꂪ�����A�o��������̉ƂȂ̂Ƀu�b���Ă��܂��I�Ɩ{���Ɏv���܂����B��l�ƈ�C�����|�̒��Őg�����o���Ȃ���Ԃł����B(��_��;) ��◎�������Ă���A����𒅂��ĉ��O�֏o�ċߏ��̊F����Ƃ��炭�ꏏ�ɂ��܂����B�������g�ɉ����ĉƂɓ�����A�R���ԂقǐQ���̃x�b�h�ʼn��ɂȂ�ȊO�͋��Ԃ̃\�t�@�[�œ�l��C����Ȃ�����߂����܂����B �@�h��̑傫�����ɂ��Ɠ��̔�Q�͏��Ȃ��A���ւ̔M�ы���������K���X������Đ��Ƌ�������o�����ƁA���d�̕���Ɛ_�I�̒u������ɎU�����A�ԕr���|��ĊD�Ɛ����T���ꂽ���ƈʂł����B �|�����v�͎~�܂�A�e���r��p�\�R���͈ړ��͂������j���͖����A�Q���ɒu�����K���X�˕t�����I�͂��̂܂܂ŁA���Ԃ̉Ƌ���ُ�Ȃ������B���ɂł͏��I���ꕔ�ړ��������A�{�̎U��������܂���B ���z���ɉƋ��K�v�ŏ����ɂ��s�p�i�����ׂď����������ƁA��K���������Ƃ���Q�����Ȃ������悤�ł��B���������z�O�ŁA������R�������ÉƂł��̒n�k�����Ƃ������ςȏ�Ԃ��z������܂����B �~�n���ł͒�����U�����|���u���b�N���̈ꕔ�ɂЂт�j�����o�����x�ł��B �s���ł��k�������r�I���ꂽ���̒����i���s�X�k���j�ł́A�X�����d���E�J�������j�����������E����和���|�ꂽ��������A�����̕ǂ�Ƌ�E�K���X��H��Ȃǂ��j���U��������Q�������A�Ɖ��̔���ȏ�͋H�̂悤�ł����B  �@���щƂ̕�n�͒����s�쓌���̋u�˂ɂ���A���ӂ͓��H�Ɖ��Ƃ���Q�������o���n��ł��B��ŕ��������̂ł����A�悪�|��A�y����ꕔ����đ傫�Ȕ�Q���A���̕����ɂ͂P�O�O���~�ȏ�̔�p�������鎖�ɂȂ�܂����B �@���щƂ̕�n�͒����s�쓌���̋u�˂ɂ���A���ӂ͓��H�Ɖ��Ƃ���Q�������o���n��ł��B��ŕ��������̂ł����A�悪�|��A�y����ꕔ����đ傫�Ȕ�Q���A���̕����ɂ͂P�O�O���~�ȏ�̔�p�������鎖�ɂȂ�܂����B�@�������H���̔z�z�Ȃǂ�����܂������A�d�C���������~�܂邱�ƂȂ��A�K�X�͐k�x�S�ȏ�Ń��[�^�[��������~���܂������A�����̑[�u������Β����Ɏg����悤�ɂȂ�A���ʂɐ������o���܂����B �@�]�k�������A�P�O�����܂łɐg�̂Ɋ�����n�k�͖�U�O�O��i�����k�x�V��1��A�k�x�U���S��A�k�x�T���P�O��A�k�x�S���R�O��j������܂����B ���������P�����Ԃɂ͗]�k�W�O�O���A���҂S�O���A���p���҂͂U�T�O�O�l�i�s�[�N��10��26���ɂ͂P�O���R�O�O�O�l�]�j�ƂȂ�܂����B �@1�O���Q�U���A�E��������z�V�����͕����̌����݂��������A�k���������}���S�x����ʃ}�q�������B��A���̒��j�ɓd�b����B�������ɏo�ȗ\��ŏ������Ă����ȂƁA�`��i���̑�������肢���Ă����j�̎��Q���͖����ł��邱�ƁA����������̌���Ƃ��l�сE�j���Ƃ���̃��b�Z�[�W�����[���ő��邱�Ƃɂ����B �����P�O���S�O�����A�k�x�T���i�L�_�ł͂U��j�̋����]�k�������B �@�P�O���R�P���A���j�������A���s�E��b�R�̃z�e���ɂāB ���̗l�q�͌���r�f�I�Ǝʐ^�Ŕq�����鎖�ƂȂ����B �@�P�P���͒g�����A�L�^�I�����ƂȂ����B�܂��Еt���Ă��Ȃ������Ԗ�R�쑐�̔��ƒI�ނ��A�r�̋�����Ȃ��班�����ړ������B�@�̏d�T�V�A�Wkg�B �@�P�Q���U���A���R�ɏ��Ⴊ�~��A���R�������Ȃ����B �@�P�Q���W���A��N���x�ꂽ���A�����Ǝ҂������~�͂������A�~������̏������ƂƂ̂����B �@�P�Q���P�O���A�����o�X�𗘗p���āA�V��a�@�O������f�B�����g�Q���B�e�̌��ʁA�x�c�搶�̐f�f�́u�@�܂ꂽ2�{�̈ڐA���̂����A���Ǖt���ňڐA�����C���͊��S�Ɋ������Ă���B���r��������ĈڐA�����C���̍��ܕ���  ��������ǂ��Ȃ��B�@����̎g�p�𑱂��āA���̊O���f�@���܂ŗl�q�����悤�B�v�ł������B ��������ǂ��Ȃ��B�@����̎g�p�𑱂��āA���̊O���f�@���܂ŗl�q�����悤�B�v�ł������B�@�P�Q���P�W���A�O�r�������Čߌ�̎U���ɂ��čs���A�r�������������ŋL�O�ʐ^�i�E�j�B �@�P�Q���Q�Q�`�Q�S���A�Ⴊ�~��̂ŁA�f�W�J���ʐ^���������g�����N������ɐ�O�����B�Z���^�������������Ĉ����������B �@�P�Q���Q�R���A�k�x�S�i�K�X������~�j�A�Q�T���k�x�R�A �Q�W���k�x�R�i�k���̎��͂T��j�Ɨ]�k���������B �Q�U�`�Q�W�������݂��ꂪ�~������~��B �@�P�Q���R�P���A��P�����~��ς���i�ō��C��-�O�C�Q���j�B �߂��̐_���_�Ќw��͍Ȃƒ��j�ɗ��ށB �@�Q�O�O�T�i�����P�V�j�N�A���U�A�Q���Ƃ��Ⴊ�~���������   �ϐ�Q�Qcm�B���͊�ђ�삯�������B �ϐ�Q�Qcm�B���͊�ђ�삯�������B���͑���𒅂���ƃS�����C�������Ȃ��̂ŁA�ᓹ�̊O�������o���܂���B�����Ȃ��̂ő̏d���T�W�A�Skg�ƂȂ�B �@�P���R���A����B�A�Ȃ��Ă������j�v�w���A��B �Z�����y�����ЂƎ����߂��A�Ƃ̒����Â܂����B �@�P���X�`�P�Q���A�~�Ⴊ�����A�U�Ocm�̐ϐ�ƂȂ�B �@�P���Q�P���A�V��a�@�O����f�̓��B �����g�Q���҂��̊��҂����Ȃ��ăX���[�X�Ɏ�f�B ���ܕ��̒����ǂ��A�����Ȍo���i���ʐ^�j�ł������B ���̂悤���C���ڐA�҂̑啔���i���Ɏq���j�͈�x�͍��܂��Ă���̂�����Ƃ̂��ƁB �������A�u�Ď�p����P�[�X�͖����̂ŐS�z���Ȃ��悤���v�Ɩx�c�搶���b���ꂽ�B �@�P���Q�T�`�Q�X���A�V����ǂ��A��������w��ǂ̐Ⴊ�������̂ŁA����𒅂��ĊO���������B ���U���ɂ��ĕ����A�Ϗ܋��X�֏o��������A���ꂽ�X�[�p�[��z�[���Z���^�[�ւ̔������ɂ����s���A�����v���P�������z�������������B �܂��A���̓����ɋ͂��ł͂��邪���̓˂��o�����������A�v���X�`�b�N����̈ꕔ�Ɠ������Ēɂ��Ȃ����B�����ő���̒ꕔ�ɒ�~����P���Ƀ{�[�����P���������ē���A�v���X�`�b�N�̈ꕔ����������ē����肪�����Ȃ�悤�ɒ��������B �@�P���R�O���A�Ⴊ�{�i�I�ɍ~��o�����B�ϐ�R�Ucm�B����͒������ɁA�Ƃ̒��ŕ���T�C�N���^���A  ����ɐ������ċؓ��g���[�j���O������B ����ɐ������ċؓ��g���[�j���O������B�@�P���R�P���A�ō��C�����P�A�O���Ɗ����A���Ԃ���Ⴊ�~��ς���A�ϐ�V�Vcm�ƂȂ�B �@�Q���P���A���x�����o��B�ō��C�����O�A�Q���ɂ����オ�炸�A�[���U���܂ł̂Q�S���ԂłX�Pcm���ς����B���a�U�P�N�ȗ��P�X�N�Ԃ�̑���Ɣ��\����A�������ϐ�P�T�Rcm�i���o��\�����͂R�O�Ocm�O��j�ƂȂ����B ���̒��A���]�ÂɏZ�ޗF�lA�N�i�ŋ߉�@��������������A��w����S�N�Ԑ�U�������j������Ő������B�@ �U�P�A���O�����v�������B �@�Q���Q���A�܂�ꎞ����A���x��͉������ꂽ�B ���A����𒅂��Č��ւ����܂ł̐�@�������B  �@�Q���R���A�܂�ꎞ��A���A���H����̃u���g�[�U�[����X����O�ɉ����t���Ă������̂ŁA�o��������J����̂���ρB���A�Ȃ����̐ቺ�낵�����āA�������ɂ��Ă��̐������������B �@�Q���R���A�܂�ꎞ��A���A���H����̃u���g�[�U�[����X����O�ɉ����t���Ă������̂ŁA�o��������J����̂���ρB���A�Ȃ����̐ቺ�낵�����āA�������ɂ��Ă��̐������������B�@�Q���S�`�T���A�P�X�N�Ԃ���剮���̐ቺ�낵������B�S���ł͂Ȃ������̎��͎O���̈�ʂ𗎂Ƃ����B �������C�͗����Ȃ��̂����A����ɉ��C�𗚂�����ԂŁA�T�d�ɉ����ɏオ���đ�����߂Ȃ��珜�������B �@���̓~�́A��p�Ƒ��߂������Ȃ����Ƃ��������A�E�r�̌����������Ȃ������w�̊O�������Ă��ɂȂ�c��Ē��y���B �܂��O������̂��ߐl�����w�̐e�w�����ɂ��Ȃ�A�X�|���W��̎w�ԃp�b�h�����ށB�����C���ƃ��b�O�E�H�[�}�[�𒅂��A�w�����ɂ̓N���[����h���ă}�b�T�[�W����B �i�N�����Ɠ������ɂ͗����̂��ׂĂ̎w���㉺�ɓ������^���͂R�U�T������Ă���̂����E�E�j �@�Q���Q�R���ɏt�P�ԁA�Q�T���ɏt�Q�Ԃ̕��A�C�����W���ɏオ�����B �������A��������R���T�����܂ł͋C�����Ⴍ�A���X��B�R���P�R�`�P�S���͋C�����O�A�T���܂ł����オ�炸�A�R�Ocm�قǂ̐ϐ���������B �@�R���P�W���A�V��a�@�O����f�B�o�߂͏����ŁA����𒅂����ɊO�������邱�Ƃ���������B ���̎�f�͂R������ŗǂ����낤�Ɩx�c�搶�Ɍ�����B �Ȍ�A�����ł����g���Ă������t����g��Ȃ����Ƃɂ����B �@�R���Q�O���`�R�P���A�Ƃ̓����Ɠ쑤�̓��H�ɏ���u�����ς�ł�������X����X�R�b�v�Ŋ����ď��Ⴗ��B�@�����A�������̊y�����d�J���B�����v�͂T��`�W����ŁA�̏d�T�V�A�Vkg.�ƂȂ�B �@��N��菭���x��āA�����������߂Ƃ���t�̑��Ԃ�c�o�L�̈ꕔ���J�Ԃ��Ԏʐ^�̎B�e������B �T�M�\�E�E�g�L�\�E�E�T�������Ȃǃ~�Y�S�P�A���̔����A���ւ��A�Z�����y�����G�߂��}�����B
 �@�S���ɓ����āA�|���r���Z�b�g���ċ������O�Ɉڂ��B �@�S���ɓ����āA�|���r���Z�b�g���ċ������O�Ɉڂ��B�~�͂��̔��ꕔ�͂����āA���̐A�ؔ������o���ē��ɓ��Đ���������B�A���~�̒I���Z�b�g���A�����ړ������ׂ��B �@�S���P�P���A�悤�₭�����Ǝ҂����ē~�͂������B �Ȍ㌎���܂ŐA���ւ��ɒǂ���B�P���ɂU��`�P�����ʁA�̏d�T�V�A�Pkg�ƂȂ�B  �@�S���P�T�������猢�U���ŏ�������i�_���E�����E�Օ��Ȃǁj�̍����J�Ԃ��n�߂�B�P�X���ɏ�������Ă��������]�i�p���H�j�̍��i�E��ʐ^�j�����ɍs���B �@�S���P�T�������猢�U���ŏ�������i�_���E�����E�Օ��Ȃǁj�̍����J�Ԃ��n�߂�B�P�X���ɏ�������Ă��������]�i�p���H�j�̍��i�E��ʐ^�j�����ɍs���B�@�T���P���`�U���A���V�������A�Ƃ̓쑤���������B ���N�͂܂��Q�����B�Ǝ҂����ꂽ�R�̐ԓy�͐�̏d�݂Ōł܂��āA�@��N�����̂ɋ�J���܂����B �R���|�X�g�i�v���X�`�b�N�����S�~�����e��j�ō�������Ɛ��͔������B �A�X�p���K�X�Q���E�H�p�e�Q��E�L���E���E�i�X�E�g�}�g�E�s�[�}���E�V�V�g�E�E�V�\�e  �P����A���t�����B �P����A���t�����B�@���̎���ɂ́A���A���ň�ĂĂ��������S�E�m�i�V�E�~�E�v�����Ȃǂ��ʎ��⃀�N�Q�E��R��E���N�����Ȃǂ��Ԗ��������ňڐA�����B �@�T���Q�O���`�R�P���A�����Ǝ҂ɗ��݁A���j�͋x��łP�O���ԁA�����m�S���Œ�̍��ς�������B �g���b�N�ŗp�y��������A��̈ꕔ���ڐA�����B �N���[���Ԃ��g���Ē�̈ړ���z�u������B���z���Ēr���A���r���̐ݔ����{���ăR���N���[�g��łB �V���ɓ��ꂽ���̂́A�r����̍����P�{�ƃc�c�W�S���A���ɒ��C�E�x�m��Ȃǐ��̊�A�ጩ���U�P��ƕ~�R�O�����ɒlj������B �V�����o�����r�ɂ͂Q�S���ԏa������𓊓����āA��x����S������ւ��āA�h�ߋ@�Ő����z����B�@�U���T���A�r�ɋ����Ɨc�������B �@���܁E�n�k�E���̓������łP���N�]��B�Z��̉��z����O�\�E��̐�������ʂ�I���B �@ |
 |
 |
 |
| �쑤�A���֑O�ʘH�e�@ | �����̎��A���ɒr | �@�@�@�@�V�����r |
| �@ �@ |
|---|
�@�`�@ �Ɖu�����ቺ�H- �̒����ٕρH - �V�����@�a�E�u��ᇐ��咰���v���E�E�E�` �@ �@�@ |
| �@�S����������A�f���I�ɉ����Ǐn�܂��������B �������t�͔��A���̐A���ւ���ƂƎ��X�ɊJ�Ԃ���Ԃ̎ʐ^�B�e�Ƃɒǂ��A�T���͔������̍�蒼���Ō��\�Z�����߂��܂����B �U���ɂȂ�Ɖ�����ւ������ɉ��P���ꂽ�Ɗ����܂����B���ςP�����͕����A�̏d�T�Ukg�ʂł��B �@�U���P�U���A�V��a�@���`�O�ȊO������f�B�����g�Q���B�e�ŋr�Ɉُ�͖����B �x�c�搶���u��Q�ҏؖ��v�̏��ނ��������Ă��������A����A�����s�����̕����ۂɁu��Q�Ҏ蒠�v�̐\��������B�i�V���W�����T���Ō�t���ꂽ�j �U�����{�A���I�ۂ��ĕ��p��������ʂȂ��A�����������B �@�V���ɂ́A���̃S���S���E�O�[�O�[�Ƃ������肪���܂��āA����̕ւ������Ȃ����B �Ǝ�����̏����ɐ����o���B �W���A�Ƃ̖k���ɒʘH�Ƃ��Ċۂ���i��e�R�������C���^�[�l�b�g�ōw���j��z�u����B �W�����ɂ͉����Ǐ��܂�A���]�Ԃɏ�����i�Q�O�O�R�N�T�����ȗ��Q�N�R�����Ԃ�Łj�z�[���Z���^�[��X�[�p�[�A�M�ы��X�ɂ��s����l�ɂȂ����B �@�Q�O�O�T�N�X���R���i�������������j�A����ɒɂ����o�ė����ɂ����ɂ�����Ⴢ��܂Ŋ�����悤�ɂȂ�A�Q�Ԃ���łĂȂ���ԂɂȂ����B �@�X���U���A�䖝�ł�������ɋ߂�����a�@���`�O�Ȃ���f�����B �V���Ȃ̂Ōߌ�Q���߂��Ă悤�₭�f�@����BMRI�̗\������āA�ɂݎ~�߂̖���������ꂽ�B �����ɂȂ��Ă����ɂ͕ς�炸�A���U���ɂ��t���Ă����Ȃ���Ԃł������B �@�X���P�R���A�ߌ�S�������l�q�h��������B�g�̂��Œ肵�����Ȃ��̂ŁA�ɂ݂̂��ߔ��ɋꂵ���Ď��Ԃ͂Q�O���ʂ��������䖝�̌��E�Ƃ��������ł������B ���P�S���A���`�O�ȊO����\���f����BMRI�̌��ʂ����u�z�ł̒ŊԔw���j�A�v�i��̍��̊Ԃɂ���ŊԔ̈ꕔ���͂ݏo���_�o������������j�@�Ɛf�f���ꂽ�B �ɂݎ~�ߖ�ŗl�q�����A��������Ύ�p�����Ȃ��Ƃ̂��Ƃł������B �X���P�V���A���M�E���ɂ͖������o�����ē��ɂS��قǂ̉����������悤�ɂȂ�A�ɂݎ~�ߖ�̕��p���~�߂āA�s�̂̉����~�ߖ������ł݂�B �@�X���Q�Q���A�V��a�@�O����f�B�x�c�搶�Ɏ�̃w���j�A�̂��ƁA�ݒ��̋��b���B ���̊�]����߂��̗���a�@���Ȃւ̏Љ��������Ă����������B �@�X���Q�U���A����a�@��������Ȃ���f����B�����̂��ߌ��t�ƕւ̍̎�����A�����P�{����ł����������~���A���H��A�����̏���������ނ悤�w���i�厡��͂Q�O�ˑ㏗����t�j���ꂽ�B �����ɂ͌��ɁE�r��Ⴢ��]�芴���Ȃ��Ȃ�A������Ŗ���āA���������ɂ��Ă�Ⴢꂪ���Ȃ��Ȃ��Ă����B �@�P�O���W���A����a�@��������Ȃ���f�B���t�����E�����̌��ʂ͂Ƃ��Ɉُ킪�����B ������������͌����������Ǐ�͎��܂�Ȃ��B �ŏI�����Ƃ��āA���߂Ă̈݃J���������Ƒ咰�����������̗\�������B �@�P�O���P�X���A����a�@�ւP���̌������@������B �ߑO�P�O���S�O���`�P�P���P�O�����܂ŁA���o�����Ə�r�ؓ����˂����Ă����݃J���������B �v�����قǂ̋�ɂ͖����������A�݂ɂُ͈킪�F�߂�ꂸ�|���[�v�����������B �a�����Ȃ������̂ŁA��������A��Ē��H���Ƃ�A�Q���R�O���߂��ɓ��@�B ���قV�K�̂a�V�V�V���֓���B���̎��̌v���l�͐g���P�T�T�A�Rcm�i�E�r���ڐA��p�̍ۂQcm�Z���Ȃ��Ă���̂Őg���������k�ށj�A�̏d�T�Ukg�A�̉��R�U�A�V���A�����P�O�U�|�U�O�ł������B �a�߂ɒ��ւ��A�Ō�t�����f�ƌ����ɂ��Ă̐�������B �T���S�T�����[�H���a���ɔz��ꂽ�B�@�@��炩�����сA�A�������A�B�T�g�C���Ɠ��̎ϕ��A�C�~���Е��̂S�i�Ŗ��X�`�͖����B �U���߂��Ɏ�p�S����i�厡��Ƃ͕ʂ̈�t�j���������Ď��̒��̏��A�����̌�����������Ă��ꂽ�B ��X���O��������従����i��i�K�X���`���j�����܁i���L�\�x�����j���R�b�v�̐��ɗn�����Ĉ��ށB ���Q�O���A�����S�����牺�܃j�t���b�N�i���ǐ��t�j�Q�k���Q���Ԃ����Ĉ����B ���݂ɂ������咰�̒�������ۂɂ���K�v�����邩��d���Ȃ��B �P�k�ȏ���T���Q�O�����A�Ō`�ւ��o��B�T���S�O�����t���ւ��o��B �U���P�O���A�U���R�O�����ɉt��ցi���z��l�Q�ȂǗL�`�����܂܂�Ă����j���o��B�V���S�O���A�F�͔����Ȃ����������Ē��a��������̂ŁA�u����ł͌����ł��Ȃ��v�ƌ��ɗ����Ō�t�Ɍ����A�P��ڂ̟�����������B�@�W���߂��ɂT�O�Oml�����܂��Q�{���ꂽ���A�܂����F�ɂȂ��đʖځB�@�X���߂��ɂR��ڂ̟����ł悤�₭�����ɋ߂������o�Ăn�j�ƂȂ�B �����O�́A���̒�������ɂ��邽�߂����ŐS�g�Ƃ��ɔ��Ă��܂����B �a�����猟�����ֈړ����ĂP�P���`�P�P���R�O���ʂ̊ԁA�咰��������������B���߂Ă̑̌��ŋْ������������������̂��A���x���咰�J�������X���[�X�ɂ͓���Ȃ��B ��t�ƌ����Z�t�Q�l������ŕ������������������������P������Ƃ�������������ł������B ���j�^�[�������ł����邱�Ƃ��ł������A�咰�̖��[�P�Ocm�ʂ̏��ɉ���������A�����̂��ߔS���g�D���T�ӏ��قǐ������B �����|���[�v�������������ƂɈ��g���A�g�D�����̌��ʂ�҂��ƂɂȂ����B ������A�L���̃\�t�@�[�ŃJ���e�L���҂��̊ԂɁA���������ċꂵ���Ȃ�g�C���ɋ삯���ށB��C����������R�o�Ċy�ɂȂ����B�咰�J�����̑}������C���ꏏ�ɑ��荞�ނ̂ŁA�I�i�����o���悤�Ɍ���ꂽ�̂����A���܂��o���Ȃ��������߂ł��B �@�P�O���Q�X���A����a�@��������Ȃ���f�B�咰�����������Ƒg�D�����̌��ʂ���u��ᇐ��咰���v�Ɛf�f���ꂽ�B�O���ŗl�q�����āA������������@�Ƃ���ꂽ�B�@((+_+))�@ �����珈�����ꂽ�y���^�T�Ƃ�����i���܂Q�E���E�[�H��ɕ��p�j�����ށB �@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂĂ݂�Ɓ@�u�咰�̔S���ɉ��ǂ�������ᇂ�т�ł��A������S�������N����a�C�B�����s���i�Ɖu�ُ�����L�͂����j�ŁA�����ł��Ȃ���a�̈�B�������i�ĔR���j�Ɗɉ��i�����j�����J��Ԃ��A�d�lj�����Α咰�S����؏����������Ȃ��B�v�Ƃ������B �H���Ö@�̖{���Q�l�ɁA�����ƕs�n���H���@�ۂƎh������������H���������n�߂�B �y���^�T�ƐH�����e�̌��ʂ͂����ɏo�āA�����̕�����キ�Ȃ�A�r�ւ����Ɩ�̂Q��ƂȂ��ĉ����ւ͂��邪���ւ͖����Ȃ����B  �@�P�P���P�T���A����a�@���Ȃ�\���f����B�܂����X�������������̂ŁA�y���^�T1���U���̑��ɐ����܂Q���i���Ɨ[�H��1�����j��lj��������Ă�������B�i�E�ʐ^�̐ԕ�݂��y���^�T�Ŕ���݂������܁j �@�P�P���P�T���A����a�@���Ȃ�\���f����B�܂����X�������������̂ŁA�y���^�T1���U���̑��ɐ����܂Q���i���Ɨ[�H��1�����j��lj��������Ă�������B�i�E�ʐ^�̐ԕ�݂��y���^�T�Ŕ���݂������܁j�P�P�����ɂ͕֒ʂ��P���P���������A�����͖w��ǖ������肵�Ă����B �@�`���[���b�v�E�X�C�Z���Ȃǂ̏t�Ԓd����A�~������̏����ŎR�쑐�I�┫�̈ړ�������B�J�V���S�O�O�O���A���V���͂W�O�O�O���̓����ŁA�̏d�T�T�A�T����T�V�A�Okg�B����T�C�N���^���Ȃǂ̋g����������B �@�P�Q���T���A�����Ǝ҂R�����ē~�͂�����B�͂��̒��ɂ������ړ����ĐA���̑����͋x���ɓ������B �@�P�Q���X���A�V��a�@���`�O�ȊO������f�B�x�c�搶�ɑ咰�������ƁA�u�����ȕa�C���o�Ă���˂��i�r�b�N���j�A�z�[���y�[�W�͍X�V���Ă܂����H��ᇐ��咰�����o�ė��܂��ˁB �ᓹ�͓]�Ȃ��悤�ɋC�����������Ă��B�v�Ƙb���ꂽ�B �@�P�Q���P�P���A���ϐ�B�@�P�R���A���֑O�ʘH��������i�P�Ocm�ʁj�A�P�W���ɂ͂T�Tcm�̐ϐ�ƂȂ����B �@�P�Q���P�R���A����a�@���Ȃ�\���f�B���t���������āA�ُ�̂Ȃ����Ƃ��m�F����B �f�@��Ƀ\�[�V�����E�H�[�J�[����A�u���莾����Ô����⏕�̐\���ɂ��āv���������B �P�Q���Q�U���A�[���ɂ͂U�Wcm�̐ϐ�i�Ó�͂Q�W�Xcm����Q�R�Vcm���L���Q�R�Tcm�łP�Q���̍ō��ϐ�ʍX�V�j�ƂȂ�B �@�����̂P�Q���͊����A���ϋC���P�A�T���i���N�͂S�A�P���j�Ŋϑ��j��Œ��ƂȂ����B �@�P�Q���R�P���A�[��̐_���_�Ќw����A�R�N�Ԃ�ʼnƑ��ꏏ�ɏo���������K���������B |
 �@�Q�O�O�U�N�P���`�Q���A�C�ے��̒g�~�\��ɔ����A����ƂȂ�B �@�Q�O�O�U�N�P���`�Q���A�C�ے��̒g�~�\��ɔ����A����ƂȂ�B�i�����P�W�N����-�ō��ϐ�ʂ͂Q���T���̒Ó�łS�P�Ucm�ƂȂ�j �@�ō��C���������ł��P���U���Ɂ[�P�A�P���A�V���[�O�A�W���ƒႭ�����B ��N�ȏ�ɑ��̏��w���̑��Ă����Ђǂ��A�����C���ƃ��b�O�E�I�[�}�[�A�z�b�J�C�����t�܂Ŏg�����ƂɂȂ����B �@�P���W���A���i�Ђ����j�̐ቺ�낵�A�ϐ�ʂ͂P�O�Ocm�Ƃ܂����Ȗڂ����h�J�Ⴊ����Ƒ�ςȂ̂ŁA�P�Q���ɂ��剮���̐ቺ�낵�i�������͎c���Ē[���甼���𗎂Ƃ��j������B �@�P���P�T���A�����ɒu���Ă���z�~�p�̃|���r�͓����������ėc��͑S�ŁA�Ȃ��������͂��ׂĂ������ɐ������т��B �P���P�U���A�����̐ቺ�낵���������̂��A�ȂɎ��a�̍��ɂ��o��B ���܂Ō��̎U���͒����[�����Ȃ����A���͉E�r�̕s�����烊�[�h�͎������ɗ[���̎U���ɂ��ĕ��������ł������B ���̓����璩�͍Ȃ��A�[���̌��U���͎�����l�ł��悤�ɂ����B �@�Q���P���A�^�N�V�[���g���āA�s�����ŏZ���[�A�Ŗ����Ŕ[�ŏؖ��������炢�A�ی��������莾���i��ᇐ��咰���j��Ë��t�̐\���ɍs���B�R���ɐR��������A�S���R���Ɉ�Îҏ��X������Ă����B�Ȍ�A�������S�z�⏕����L����Ƃł��B �����̊����͂Q�����{�܂łŁA�ϐ���P�Q�Ocm�ʂőO�N��菭�Ȃ��A���{�ɂ͎��]�ԂŃz�[���Z���^�[�ɍs����悤�ɂȂ����B ���Ɠ�̓��H�e�ɏ���u�����ς�ł�������X�̕ǂ������ĂP�O���قǂŏ��Ⴗ��B �P-�Q���́A�S�O�O�O�`�U�O�O�O���قǂ̉^���ʂŁA�̏d�T�U�A�T�`�T�V�A�Tkg�B�@�܂��A�咰�̒��q�����肵�������P�������ɕ֒ʂ����邪�A�����͖����Ȃ����B �@�R�������甫�A�����͂�����I��ɏo���A�A���ւ���Ƃɑ�Z���B �@�S�����{�܂łɁA���A���̃u���[�x���[�E��䕗ނ̉ʎ���A�n�i�~�Y�L�E���}�{�E�V�E�L�����N�Z�C�E�T���X�x���Ȃǂ̉Ԗ��Q�O���ʁA���ނR�O�������ɈڐA����B �@�����͒r�ɕ������������ɁA�J���X�ɂ���āA�I�����_�V�V�K�V�����Q�C�ߐH����Ă��܂����B�����ɒr�̎���Ƀe�O�X����ƃJ���X�͊��t���Ȃ��Ȃ����B ���X�ƈ����͈�Ăɍ炭�G�߂̉ԁX�B�ʐ^�B�e�ɑ����̎�����������B �@�T���ɓ����āA����V���ɂQ������ؕc��A����B�܂��A���X�����C���̓�������A���ɔS���ցi�咰�̔S���g�D�ƌ��t�����������A�~����ׂ����悤�ȕցj���o��悤�ɂȂ����B �@�T���P�X���A����a�@�Ŏ厡��̌��搶�ɂ���咰�o���E�������������B�i���������������������������߁H�j�@�O���̗[�H�͕a�@����n���ꂽ���ʐH�i���g���g�H�j�����ɂ��A��A���܂�����łP���߂�����R��g�C���ɒʂ��ĕ��̒�����ɂ���B �����͂X���T�O������R�O���قǂ̌����ŁA��傩��o���E�������݂̌����Ɠ�  �l�ɐg�̂���]�����A�̈ʂ�ς��Ȃ��烌���g�Q���B�e������B �l�ɐg�̂���]�����A�̈ʂ�ς��Ȃ��烌���g�Q���B�e������B�咰�ɑ傫�ȕω��͖����A�������قǑN���ɂ͐f��Ȃ��悤�ł����B �@�~�̊Ԃɒ�̏��̖ɑ������������i�Ⴊ���������̂Ŏ��t�����ł����j�B�����́A�Q�O���N�O�ɏ��w�����������j�ƈꏏ�ɍ�������̂ŁA�V�W���E�J�����Y�����������������L�O�i�ł��B ���z�Ŋ����ς�������Ƃ������āA�X�Y������������ĂT�����ɂ͖����������Ă������B�i�E�ʐ^�j �@�U���X���A�V��a�@���`�O�ȊO������f�B �E�r�̎�p����Ԃ��Ȃ��R�N�ƂȂ�o�߂������Ȃ̂ŁA����͂S���������ɔN�R��̗\��ŁA��Ɋ��̔x�ւ̓]�ڂ����������`�F�b�N���悤�Ɩx�c�搶���b���ꂽ�B �@�V�������J�������A���Ǝ��Ԃ����ɏ��Ȃ��A�~�J�����͂V���R�O���ƒx���Ȃ����B �@�W�����ҏ��ƂȂ��āA���d�ʁE�d�͏���ʂ͉ߋ��ō��ƂȂ����B �䂪�Ƃł͎Ă���s���ŕ��������炸�A�O���������������ē��Â��邱�ƂɂȂ����B �����v�P���U�O�O�O�`�P�Q�O�O�O���ŁA�̏d�͂T�U�A�T�`�T�V�A�Tkg�ƂȂ�A�֒ʂ͂P���P��܂��͖����A�Q��≺���͂Ȃ������Ԃ��������B �@�W���P�T�`�Q�O���A�T���ԘA���łR�T���ȏ�ƂȂ�A�ō��C���͂P�V�����R�W�A�S���ƂȂ����B �@�W���Q�P���A�ȑO�����������̂ɃK�}�����Ă������̎��Â̂��߁A�߂���������@�ɒʉ@����B�P�P�����{�܂Ōv�R�O��ʂ��A�����a���i��ł��āA�O�����Ă��鎕���Q�{�����āA�u���b�W�Q�����i���P�͕ی��ΏۊO�j�A���ꎕ�P���������W�����Â������B �@�P�P���V���A�O�邩��̋����ŐA�ؔ��̖w��ǂ��|���ł��~�����B ���͂��̂܂܂Ōߌ�Q������a�@�Ɍ������@�����B���W���ŏ��̌�������P�N��Ƃ������Ƃ��咰��������������B �O��Ɠ��l�ɖ��O�ɉ��܂����ނƁA�Q���߂��ɌŌ`�̔r�ցA�S���������r�ւ̒���ɕn���H�f���C�Ɨ�⊾�ŋC���������Ȃ��ē|��A�g�C���e�ɂ���k�b���̈֎q�ɉ������B �Ō�t�̎蓖�ĎR�O���قǂ��̏�ŐQ��B �T���ɕ����ɖ߂��āA���ǐ��t�E�j�t���b�N�Q�k�����ށB�U���������物�F������ւ��S��o���B�S��ڂ̂W���T�O���A�����ɋ߂����ւł��邱�Ƃ��Ō�t���m�F���A�n�j���o���̂őO��̂悤�ɟ����͂��Ȃ��ł��B���̌�S���ԋ߂��a���̃x�b�h�ŋx��Ō����̘A����҂B �P�Q���T�O���`�P���R�O���A�厡��̌��搶�ɂ��咰��������������B���̂��J�����̑}��������̓X���[�X�ɍs�����B ���ʂ͒�ᇕ����������Ȃ��đ咰�̖��[�Scm�ʂ̏��Ɍ��肳��A��Ԃ��D�]���Ă����B |
|
| �Q�O�P�P�A�O�Q�C�O�R�A�@�ߕ��̓��@�@�lj��X�V |